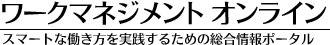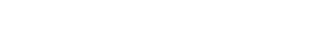【ビジネス用語】MBOとは?目標設定や評価におけるOKRとの違い
組織マネジメントにおいて、近年は上司による上意下達ではなく、従業員がそれぞれ主体的に行動できる組織づくりが重要視されるようになっています。組織マネジメントのひとつの概念であるMBOについて、概要やメリット・デメリットなどを解説します。
人事評価にも利用できるMBOは、企業が従業員に目標を与えて経営や目標管理を行う手法のひとつです。従業員のモチベーション向上はもちろん、成果主義に基づく人事評価ツールという観点からも、MBOについて詳しく知りたいという担当者も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、人事におけるMBOのとらえ方からもそのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
OKRとの違いも意識しながら、理解を深めましょう。
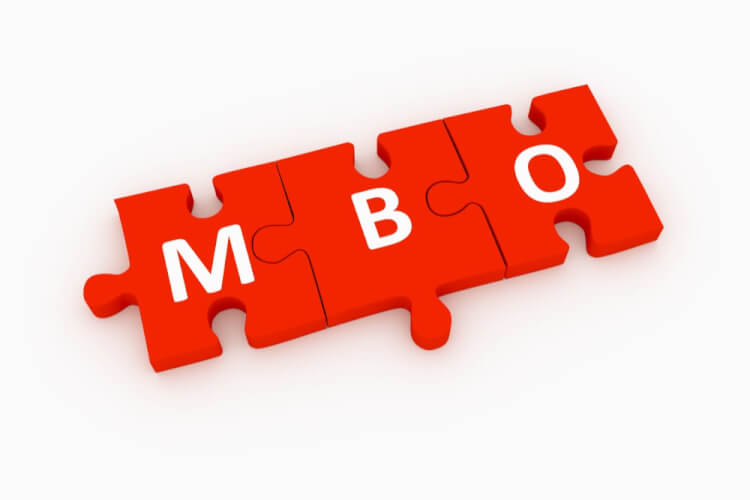
MBOの意味とは
MBOとは、"Management by Objectives"の略で、直訳すると「目標による管理」という意味です。経営に関する著書が多数あるピーター・ドラッカーが『現代の経営』のなかで提唱した概念であり、正確には「Management by Objectives and self-control」と表記されています。組織マネジメントにおける概念で、個人や組織ごとに目標を設定し、その達成度によって評価を行います。目標管理により、「支配」の意味合いの強かったマネジメントが「自己管理」へと転換され、それによって各従業員のパフォーマンスが引き出されると考えられています。
このドラッカー氏の理論の根拠となっているのは、心理学者であり経営学者でもあるダグラス・マクレガーが著書『企業の人間的側面』のなかで唱えた「X理論・Y理論」です。X理論とは、人間には本来的に怠惰な側面があり、上からの命令や強制が必要だとし、従業員を「従わせる」ことでコントロールするという考え方です。一方、Y理論とは、人間が本来仕事好きで、自己実現のために努力していくものであるという考えであり、各従業員の自主性を重んじます。そのうえで、マクレガー氏はY理論をベースにした従業員の管理が結果として生産性向上や企業全体の業績向上につながるとしました。
なお、MBOといえば、M&Aにおいて経営陣の買収を意味する"Management Buyout(マネジメント・バイアウト)"の略としても使われますが、このMBOとは全く意味が異なります。
MBOという概念が提唱される以前の企業経営は、企業が目標を達成するために、従業員に対して業務の作業やその手順までを細かく指示して、企業活動を進めていました。しかし、社長や上司がすべての従業員に対して作業の細かな手順までを指示することには限界があります。それは、企業規模が大きいほど難しくなります。
そこで、これまでのように「すべての作業を指示する」というやり方ではなく、従業員に「目標だけを与えて業務プロセスは従業員に任せる」、そして従業員は目標達成のために必要な要素を「セルフコントロールできるようになる」マネジメントが有用だと考えられるようになりました。これが、MBOであり、ピーター・ドラッカーが提唱した「Management by Objectives and self-control」です。
また、MBOの手法では、従業員に目標を与えるだけではなく、その目標を達成できるように従業員を育成するマネジメントが重要です。
部下の一人ひとりが個人の目標を設定して実行し、自身で目標管理を行うことでモチベーション維持や主体性の向上につながるように、上司が育成していかなければなりません。その過程で、上司は部下の成長度合いや目標達成具合を評価しますので、MBOは人事評価のツールとしても利用されるのです。
MBOの導入目的
それでは、企業がMBOを導入する目的をみていきましょう。
従業員のマネジメント
MBO導入の主な目的は、従業員に対して目標を与えてマネジメントすることです。
上述したように、以前のマネジメントでは「従業員の作業をすべて指示する」というものでした。しかし、多くの従業員に対して一人ひとりの動作をすべて指示することは実質的に不可能です。そこで、従業員に「目標だけ」を与えて、「達成のプロセスは従業員に任せる」効率的なマネジメントであるMBOが注目されました。
MBOを導入することで、従業員のコントロール方法は大きく変わります。つまり、上司に求められるマネジメント能力が変化したのです。
これまで、上司は部下に対して業務の手順を一から指示して、部下は指示された動作を言われた通りにこなすスタイルでした。しかし、MBOは上司が部下に対して目標だけを与え、部下は目標を達成する手段を「自ら考えて行動」するスタイルです。
もちろん、目標を与えられたからといってすべての従業員が主体的に行動できるわけではありません。部下が目標を達成できない場合は、その部下が目標を達成できるように「上司が育成」します。
こうして、従業員が目標を達成できるスキルを身につけて主体的に行動できるように導くマネジメントが、MBOの目的のひとつなのです。
個人目標の達成
MBOでは、従業員個人が目標達成に向けて、主体的に行動できるようになることも目的のひとつです。
目標達成のためのプロセスは個人が考え、自身の力で目標を達成することが大切です。目標を達成するためのスキルを身につけ、目標管理を自分自身で行えるようになる、つまりセルフコントロールを行えるようにすることもMBO導入の目的なのです。
MBOを人事考課に利用する
MBOは人事考課としての利用方法もあります。
従業員が、目標達成のためのプロセスを考えられるようになり、業務の効率化やモチベーション向上をセルフコントロールできるようになったかどうかを評価基準として用いるのです。
具体的には、目標を達成できたか否かの人事評価基準を作成するなどが考えられます。
目標達成が評価に関わるならば、従業員の目標達成に対する意欲向上や、目標を達成するために必要なスキルアップにも積極性が出てくるでしょう。ただし、このようなモチベーションは、従業員自身から勝手に沸き起こることは難しいと考えられますので、上司が部下を育成することが必須だといえます。
MBOの特徴
MBOは「目標による管理」を意味する概念のため、ともするとノルマを管理するツールとして誤解されてしまうケースもあります。しかし、実際は組織マネジメント上の人材育成にフォーカスした方法論であることをまず理解する必要があります。そのうえで、MBOのメリットやデメリットについて具体的に見ていきましょう。
MBOのメリット
MBOには以下のようなメリットがあります。
モチベーションの向上
MBOでは、それぞれの従業員が自ら目標の達成プロセスを管理および評価していきます。つまり、自主性が極めて高い管理方法でもあるのです。組織全体の目標に紐づいた個人の目標を自己管理を通して達成していくので、自分の目標の達成が組織への貢献にもつながるということが実感しやすくなります。主体的に業務へ取り組むことで、日々の業務へのモチベーションが向上しやすくなるという効果も期待できます。
目標を達成した「達成感」は、次の目標に対する作業の効率化やスキルアップへのモチベーションにもつながります。また、従業員自身が目標管理を行うことで、仕事に対する姿勢も良い方向へ変化するはずです。
従業員の能力を最大限に引き出せる
従業員の能力を引き出すには、目標設定を慎重にする必要があります。簡単すぎる目標では手を抜いてしまいますし、反対に高すぎる目標だと達成が不可能と感じ、モチベーションが下がってしまいます。現状の能力でも、少し努力や工夫をすれば達成できるという程度の目標を各従業員に合わせて設定することがポイントになります。適切なレベルの目標を設定できれば、MBOを通して従業員の能力を最大限に引き出すことが期待できます。
人事評価にそのまま活かすことも可能
MBOは、従来は人材の能力開発に焦点を当てた概念でしたが、だんだんと企業の経営戦略や人事考課と連動した使い方もされるようになってきました。目標設定を適切に行うことさえできていれば、MBOに基づいた従業員の評価をそのまま人事評価として活用しやすくなるのです。
MBOには以上のようなメリットがありますが、これらのメリットを最大化するには、やはり目標設定が重要になります。以下に、目標設定のポイントを記します。
- 目標が明確かつ具体的であること
- 目標レベルが適正(高すぎず、低すぎない)であること
- 目標達成において時間軸が適切に設定されていること
- 目標達成に向けた具体的方法を定めること
- 会社目標と自身の目標との関連づけを行うこと
従来に比べてマネジメントがしやすくなる可能性がある
上述した通り、従来のマネジメントに比べると、MBOを導入した従業員のマネジメントの方が、管理がしやすくなる可能性があります。
従業員に作業内容を一から十まで指示するよりも、目標を与えて従業員自らに達成させる方が、上司の指示負担が軽減されるからです。
ただし、目標を達成できない従業員を育成しなければならないという点では、上司にもこれまでとは違うスキルが求められることも確かです。
主体性が向上
従業員自身がどうやって目標を達成するかを考え、行動するということは、主体性の向上につながります。
これまで指示待ちをしていた従業員でも、ひとつでも目標を達成した「自信」を得られれば、「どのように業務に向き合うか」を自らが考えるようになり、主体性を持って行動するようになるでしょう。
上司と部下のコミュニケーションが活性化
MBOで重要なのは、従業員が目標管理に対してセルフコントロールできるように、上司が育成することにあります。つまり、上司と部下のコミュニケーションがなければMBOは意味をなさないのです。
そこで期待できるのが、上司と部下のコミュニケーション活性化だといえます。
このコラムで何度もお伝えしていますが、目標を達成できない部下に対しては「上司による部下の育成」が欠かせません。部下を育成するためには、密接なコミュニケーションが不可欠です。ですので、必然的に上司と部下のコミュニケーションが活性化します。
MBOのデメリット
一方、MBOのデメリットや実行上の課題もあります。
目標設定の難しさ
MBOでは、基本的に個々に目標を設定し、その達成に向けたプロセスも含めて自己管理します。そのため、自主性が伸びるマネジメント手法である一方、目標設定にばらつきが生じます。場合によっては、組織にとってプラスにならない目標設定にもなりかねません。結果、会社全体の目標を達成できなくなるという危険性もあります。
また、MBOを中心とした評価制度の場合、従業員の心理として達成しやすい目標設定に傾きがちです。客観的に見た成果を軸にした評価と、MBOを軸とした評価にギャップが生まれてしまい、従業員間の不公平感を醸成してしまうという懸念もあります。マネジメントの担当者などが、各従業員の主体性を保ちつつ、適切な目標設定に導くということが求められます。
MBOのプロセスのなかでノルマ管理になりがち
MBOで定めた目標がいつの間にか「ノルマ」に転化してしまい、本来の目的を見失うという恐れもあります。特に、主体的に定めた目標ではなく、上司などに押し付けられた目標では、MBOのメリットは発揮されず、むしろ単なるノルマ管理となり従業員のモチベーションは下がってしまいます。
ノルマによる負担がモチベーションを下げる
MBOでは、細かな仕事の動作指示をするのではなく、目標だけを与えてプロセスを従業員が考えるというスタンスです。そこには「部下の育成」が不可欠であり、上司のマネジメント能力が大きく関わります。
しかし、MBOを導入する企業の中には、「目標を与えるだけ」で育成などのフォローをせず、目標達成できない従業員に対して圧力をかけるなどの間違った使い方も見受けられます。
この場合、与えられた目標は従業員にとっての「ノルマ」になり、達成できなければ評価に関わるといった恐怖心や負担になります。それは、従業員のモチベーション低下につながり、MBO導入の目的とは異なる結果を招いてしまいます。
高評価を得ることが目標になりがち
目標を達成すれば人事評価で高評価を得られるという意識が高まると、高評価を得るために「達成しやすい目標」を定める従業員も出てくるでしょう。
本来ならば、実力よりも少し高い目標を定め、それに向かって創意工夫することでスキルアップや達成感を得たり、モチベーション向上につながったりするものです。しかし、達成しやすい目標を定めてしまうと、簡単に目標を達成できて、人事評価でも高評価を得られますが、MBO本来の目的とずれてしまうのです。
Y理論の影響が強く個人任せになる
本来MBOは、企業の目標の達成に向けて活用するべきものですが、冒頭に紹介したY理論の影響が強まり、従業員のモチベーションアップや自主性の尊重ばかりが優先されてしまい、個人任せな組織に陥る恐れもあります。あくまで企業全体の目標における個人目標という位置づけであり、そのなかで各従業員の主体性が発揮されるという点を周知し続けることが重要です。組織のリーダーが、ときにはX理論の要素も念頭に入れながらバランスよくマネジメントを推し進めるのがよいでしょう。
MBOとOKRの違い
MBOをより深く理解するにあたり、近年注目されているOKRとの違いを考えることは有効です。OKRとは、"Objective and Key Result"の略で、直訳すると「目標と主な結果」という意味です。MBOではプロセスも含めた「管理」に焦点が当てられるのに対し、OKRでは「結果」を重要視します。会社は役職や部署などさまざまな階層の従業員から成り立っています。企業としての重要な目標を全ての階層の従業員に効率的に共有し、その達成に向けて全員のベクトルを揃えるためにOKRが活用されます。
以下では、「評価頻度」「目標設定」「目標管理」の3点に分けて両者の特徴や異なる点を解説します。
評価頻度
まず、MBOとOKRでは評価の頻度が異なります。MBOでは、目安として半年に1回あるいは年に1回程度の評価サイクルとなっています。一方OKRでは、4半期に1回、場合によっては月に1回と、細かく評価が行われます。なぜ、このような違いがあるのでしょうか。
MBOでは定性的、つまり数値化するのが難しい要素の評価も行われるのに対し、OKRでは基本的に定量的な評価のみを行う、という違いがあります。OKRは必要に応じて目標達成に向けたアクションの量や質を軌道修正していくという特徴もあるため、一定の頻度で推移を計測する必要があるでしょう。それに対し、具体的な数値のみで評価をしないMBOでは、それほど頻繁に評価をする必要はないということになります。
また、変化のスピードの速いIT業界などでは、評価頻度の高いOKRが導入される傾向にあるといえます。
目標設定
また、MBOとOKRでは目標設定の考え方にも大きな違いがあります。「評価頻度」の項でも触れましたが、MBOでは定性的な目標も含まれる一方、OKRでは基本的に定量的なもののみに限定して目標を設定します。この違いは、MBOでは目標の達成が重要視されているのに対し、OKRではそのプロセスで従業員の能力を伸ばすことに力点が置かれていることから生じます。つまり、OKRでは目標を100%達成することではなく、その過程でスキルアップなどにつなげることを考えます。目安としては、60%から70%くらいの到達率になるような、現状よりも少し高い目標を設定します。このように、OKRの目標は数字で測定できることが重要になるため、おのずと定量的になりやすいのです。
MBOとOKRでは、何のために目標設定をするのかという、目指す目的が異なることを理解しておきましょう。
目標管理
目標設定をするための目的が異なれば、その管理方法、つまり目標の共有の仕方に違いが生まれます。具体的には、MBOでは従業員とその上司間のみで共有するのが原則です。従業員自らが主体性を持って設定するという特徴から、従業員別に目標が異なり、その目標の達成が従業員の評価にも直結します。しかしながら、それを全体として一括して評価するのが難しいという側面もあるため、上司と従業員間で共有するのが適しているのです。一方、OKRでは数値的な目標を設定するため、従業員間でそれぞれ目標が異なってはいても、チーム全員でその数値目標を共有します。組織全体の業務効率化などを図るために、社内の全従業員間で目標を共有するのが基本となっているのです。
まとめ
MBOは、個人の主体的な目標設定とその達成に向けたプロセスを通じて人材を育成する組織マネジメントの概念であり、MBOを利用すれば、従業員一人ひとりの仕事に対する主体性やモチベーションアップや能力を引き出すことも可能です。また、人事評価にも利用できます。
変化の激しいビジネス環境においては、従業員が柔軟かつ主体的に動けることが大切であり、その点でMBOは効果の期待できる方法といえるでしょう。
メリットはもちろん、デメリットについても意識して、MBOの使い方を間違えないように運用することが大切です。
- カテゴリ:
- OKR・目標管理