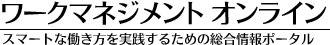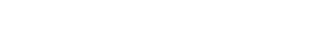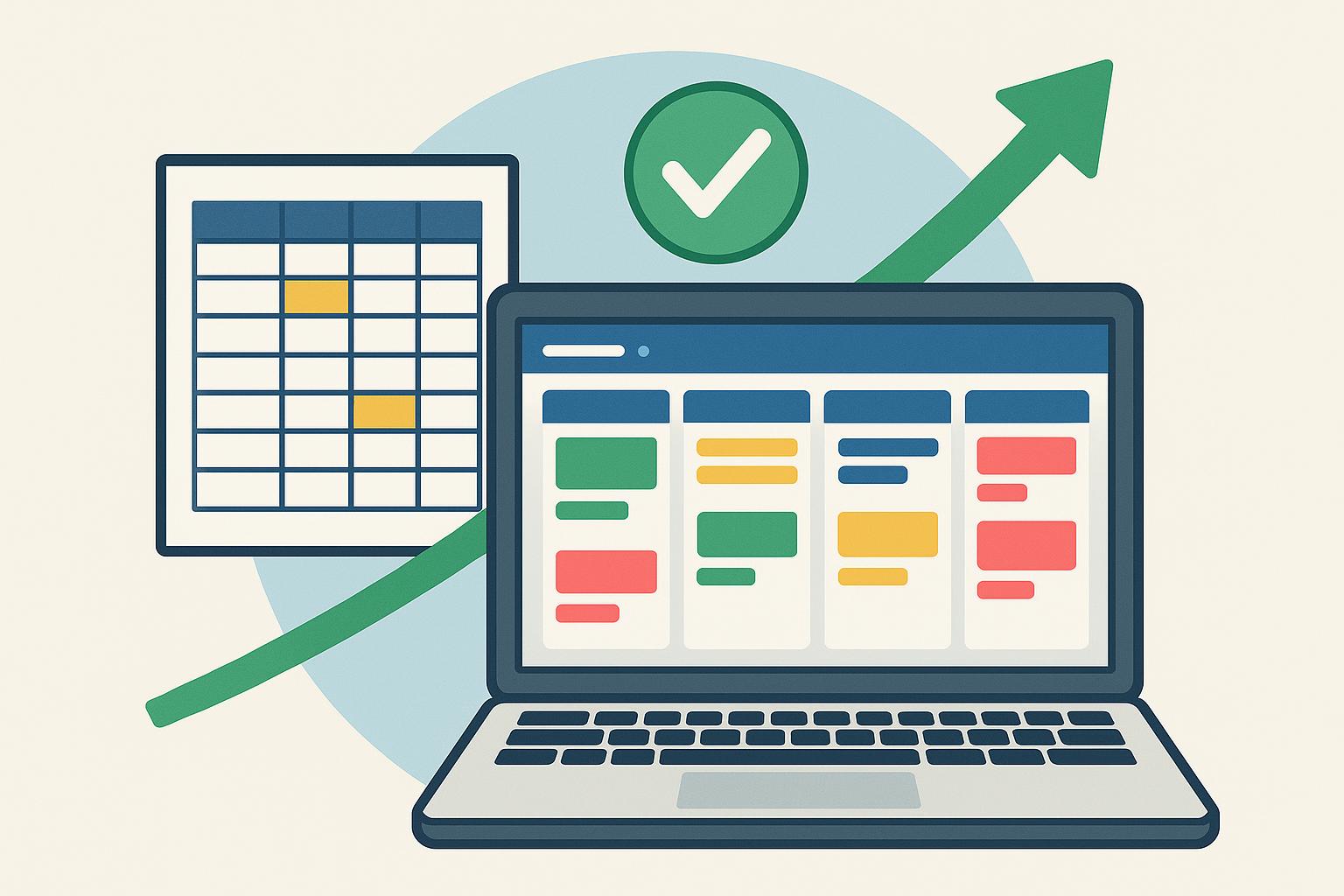AI導入とDXの実体験や実例を紹介|リーダーとチャンピオンの考え方の違いとは

Asanaが主催する「ワークイノベーションサミット東京2025」が開催されました。本イベントはイノベーションを起こすための働き方について学ぶ内容であり、実際に社内変革に取り組む企業の事例やAsanaの最新テクノロジーが紹介されました。
今回はイベントの中からリーダーズパネルディスカッション「AIの受け入れと働き方の現在地」およびチャンピオンズパネルディスカッション「現場・ミドルからのチェンジ・マネジメント」の内容をレポートにまとめました。
AI導入やDXをはじめとする組織内での変革について、登壇者の実体験や実例をもとにご紹介いただいたためぜひ最後まで読んでください。
リーダーズパネルディスカッション「AIの受け入れと働き方の現在地」

比屋根氏:株式会社三菱総合研究所で執行役員および研究理事を務める比屋根と申します。当社はシンクタンクやコンサルティングサービスの機能を有しており、私は生成AIラボセンター長として、社内DXおよびAI活用、お客様に提供するAI事業を所管しています。
和田氏:富士通株式会社の和田です。私はCorporate Digital本部の本部長として、社内変革を担当しています。現在、さまざまなトランスフォーメーションを並行して展開しており、「One Fujitsu」というキーワードのもとで、社内に数千あるシステムをオプティマイズしてシンプル化することを目指しています。
AI×働き方/ビジネス変革 課題と背景

比屋根氏:私からAsanaの導入に関する当社の課題についてお話しさせていただきます。

当社は3年前から4年前に社内DXを開始したのですが、プロジェクトを進める中でChatGPTが登場し、DXの様相が大きく変わりました。当社はリサーチ業務なども広く展開しているため、生成AIを使いこなさないと不利になると感じたのです。そのため現在は生成AIの取り組みに注力し、社内変革を進めています。
また、当社では毎年数千件のリサーチプロジェクトが稼働しています。中にはプロジェクト管理に失敗して炎上するケースもありました。当時はExcelを使用しており、管理の品質に課題があったのです。そこで、より高品質なマネジメントを実現するためにAsanaを導入しました。
導入時は、次の2つの点が課題となりました。
- WBS(Work Breakdown Structure)を作り込まないといけないという誤解があった
- 既存の管理方法で上手くいっているプロジェクトもあり、新しいツールの導入に抵抗があった
こうした課題はあったものの、私はAsanaを優れたツールだと感じていました。例えば、当社でアンケート調査を実施すると、その時点で数百のタスクが発生します。しかし、これらのタスク管理をExcelで行うのは工数の観点から現実的ではありません。また、多くのプロジェクトはアジャイルで進みます。柔軟に計画を変更しつつ、タスクをブレイクダウンしなければならないのです。
このようなタスク管理に柔軟に対応できるという点でAsanaは非常に優れたツールでした。現在はAsanaにAIを導入して、プロジェクト管理の品質をさらに高める取り組みも進めています。

和田氏:私からはAIと働き方改革の関わりについて説明いたします。AIはビジネスモデルや働き方そのものを変容させるツールです。現在、私たちは大きなパラダイムシフトの最中にありますが、当社では、AIおよびAIエージェントを重点領域として進めています。
AIの活用方法にはさまざまなものがありますが、当社の考えと親和性が高いのは「人がこれまで取り組んできた業務の中で、定型化・標準化できる業務を今後はAIに任せ、人は価値をより創造できる業務にシフトする」というものです。
現在、富士通全社でAIを日常的に使っているユーザーは4.9万人を超えています。2025年は、個人によるAI利用のみならず、組織プロセスおよび業務プロセスそのものにAIを埋め込むことに注力したいと考えています。また、全社でAIに関するリテラシーを高めることも重要な取り組みです。
AIの受け入れと働き方の変革 期待値とギャップ

AI導入を進めるポイント

和田氏:AI導入を進めるなかで、想定以上に難しいと感じた2つのポイントがあります。
1つ目は、AIの導入が目的ではなく、AI導入により成果を出さなければならないという点です。業務プロセスにAIエージェントを導入する際、まず必要なのは業務プロセスの見直し、不要な業務の削減、標準化です。その上でどこにAIを適用してどのような成果を目指すのかを明確化する必要があります。当社でも試行錯誤しながら進めており、AI導入の効果を定義してモニタリング・可視化することが重要だと感じています。
2つ目は、AIをどのように展開するかです。アジャイルや市民開発のように全員で盛り上がることは重要ですが、全社で効果を最大化・スピードアップするためにはトップのコミットメントが必要です。リーダー層がAIを活用し実践しなければならないのです。当社の場合、社長がITのバックグラウンドを持っており、デジタル技術への理解が深かった点がポジティブに作用しました。現在は、ベンダーと協力しながらハンズオンやワークショップで経営層にAIを使ってもらう活動を続けています。

比屋根氏:和田さんがおっしゃったことは、私がコンサルタントとして日頃から経営者に伝えている内容と同じです。私はAIの導入を進めるためには、次の2点が重要だと考えています。
- 業務改革なければDXなし、DXなければAIなし
- トップのコミットメントが重要
当社の主たる事業であるコンサルティングはアナログな業界です。中にはAIなどの先端技術を好む人もいますが、一方でそれらの技術に全く明るくない人も少なくありません。そうした中で、ボトムアップとトップダウンをどのように進めるかに現在も苦労しています。
トップダウンの動きを促すためには、私から経営陣に説明を尽くすしかないと考えています。ボトムアップの動きを促すためには、マニュアルやテンプレートを用意して説明会を繰り返すことが近道です。
実際にChatGPTを使用した途端にレベルアップするメンバーもいれば、先端技術と距離を置き続けるメンバーもいます。後者については、AIの効果をわかりやすく説明しなければなりません。例えば、手間のかかる業務にAIを活用することで工数を削減できるのであれば、先端技術が苦手なメンバーも使用を開始するのです。
このように実際の体験を促すことで、AIの普及が加速します。当社では、各部署にDXリーダーを任命し、ローカルな情報共有会を実施しています。また、Teamsの共有スレッドを活用してコミュニティをゆるく形成し、情報交換の場を設けています。
トップダウンとボトムアップ
(ファシリテーター)キム氏:トップダウンとボトムアップというお話が出ましたが、AI導入を進める上でどちらを重視すべきなどの考えはあるでしょうか?
比屋根氏:私は社風により重視するものを決めるべきだと考えています。例えば、経営層が力強く号令をかけることで全体が動くような企業は、AI導入においてもトップダウンが効果的です。一方、一人ひとりの従業員がある程度自由に動いたり、事業部ごとに動いたりするような企業はトップダウンだけでAI導入を進めるのが難しいかもしれません。
ボトムアップには下地づくりの側面もあります。これがないままトップダウンでAI導入を進めると、現場で反発が起こり導入が進まないケースがあります。
和田氏:私も両輪で進めることが大切だと考えています。現場を知っている従業員たちが工夫しながらイノベーションを起こす領域では、ボトムアップの動きが重要です。一方、組織のプロセスを変えるような領域ではトップダウンがなければ成果を得るのが難しいでしょう。
AIの受け入れと働き方の変革 今後の展望と取り組み

比屋根氏:AI業界では、2023年頃に生成AIが登場し、2025年にはAIエージェントが話題の中心を占めるようになりました。これは生成Aを個人で使う時代から、AIエージェントを組織として使う時代への移り変わりを示しています。
現在は業務特化型の信頼性の高いAIエージェントを作るのも決して難しくありません。AIエージェントは自動化できる範囲が広く、プロセスが多いため、RPAでぶつ切りになっていた業務をAIエージェントで一気通貫で自動化できると感じています。
働き方を変えるためには、いかにして自動化を実現するかを考え続ける必要があります。
(ファシリテーター)キム氏:AIは働く人にどのような影響を与えるとお考えでしょうか?

比屋根氏:AIの活用により、従業員は上流から下流まで対応できるフルスタック型の人材になれると思います。しかし、これはあくまでもAI活用の1つの効果でしかなく、本質的なところではAI活用を進めることで従業員は最終的にマルチロール化できます。
例えば、1つのイベントを開催する際、1人の従業員がプロモーションからケータリングの調達、キャッチコピーの作成に対応できるようになるのです。AIの時代では、自分の役割を広げることが重要です。
(ファシリテーター)キム氏:ありがとうございます。続いて、和田さんから今後の展望をお聞きしたいと思います。

和田氏:当社の今後の取り組みは、AIを必要不可欠なものにすることです。2024年からAIを使用し始め、便利だと実感しました。今後は、個人利用から組織利用に焦点を移していきたいと考えています。
例えば、セールスプロセスやプロキュアメント、ファイナンス、HR、サービスという実業務にAIエージェントを導入し、業務プロセスの変革を実現したいです。並行して、個人による利用を促進する取り組みも進めていきます。
現在、ワークフローやタスクマネジメントは人の手で行われていますが、いずれはマルチエージェントの環境でこれらの業務を自動化できると理想です。また、AI導入を進めることで会社として求める人材も変化するため、採用戦略も変えていかなければならないと考えています。
チャンピオンズパネルディスカッション「現場・ミドルからのチェンジ・マネジメント」


村岡氏:株式会社村田製作所の通信・センサ事業本部、通信モジュール事業部、有機機能基板商品部、開発5課でシニアマネージャーを務める村岡と申します。当社は、積層セラミックコンデンサを製造している会社として知られていますが、お客様の要求に合わせてカスタムモジュールを製造する事業も展開しています。カスタム化が必要な事業はその性質上、お客様とのすり合わせが多く、業務が煩雑化しやすいため、当社ではプロジェクト管理にAsanaを使用しています。はじめは部署内で150アカウントから利用を開始し、2025年4月にAsanaが全社標準ツールとなりました。現在のアカウント数は約4,000です。

渡邊氏:商船三井システムズ株式会社のグループデジタル推進1部で主任を務める渡邊と申します。当社グループは海運事業を営んでおりますが、海を中心とした社会インフラ企業への変革を目指し、現在はより安定したポートフォリオを構築する取り組みを進めています。その中で、プロジェクト管理を効率化して、より価値創造業務にリソースを割くためにAsanaを導入しました。

原田氏:KMバイオロジクス株式会社のCMC技術開発本部、品質技術開発部、品質統括課の原田と申します。当社は、インフルエンザワクチンを主力製品とし、医薬品の研究開発から販売までを一貫して手がける製薬企業です。私は、製品の品質向上およびそれに注力するためのDX推進、AI活用を担当しています。業務効率化の一環としてAsanaを導入し、日々の業務改善に取り組んでいます。

DX/AI推進の壁
村岡氏:当社がAsanaを導入したのは2022年でした。当初は、標準ツールでないものを会社に導入する際にセキュリティと費用の面でハードルがあったことを覚えています。マネジメント層としては、一定の費用がかかるツールを使いこなせるか、どのような効果を実現できるかを丁寧に確認する必要があったのです。
しかし、実際に私がAsanaを使用してみると、UIがユーザーライクであり、業務工数削減に寄与することがわかりました。このような実績をマネジメント層に伝えて、最初に150アカウントで使用を開始し、その後は社内イベントでAsanaを紹介したり、どんなツールなのかという疑問に答える場を設けたりしました。このような繰り返しが現在の全社導入につながったと考えています。
渡邊氏:Asanaの導入について、当社には2つのハードルがありました。
1つ目は、数多あるツールの中でなぜAsanaを選ぶのかという点を明確にすることです。2つ目は、上長のみならず担当者にとって使いやすいツールかどうかを説明することです。実際のところ、上長と担当者ではAsanaの使い方が違います。
当社は当初、CTIO(最高技術イノベーション責任者)が船舶の出航管理に使う目的でAsanaを導入しました。この取り組みは成功し、500名規模でAsanaを使うようになりましたが、情報入力者に目的と効果が見えにくく、情報入力の粒度に問題が発生しました。このような問題を一つずつ解決し、導入のハードルを下げる取り組みが現在のDXにつながっています。
原田氏:当社の場合、現場の人にAsanaの導入について納得してもらうことが壁でした。当社は2024年12月頃にAsanaを導入したのですが、初期には「メールやTeamsでできているのに、なぜわざわざAsanaを使う必要があるのか」「二度手間では?」といった多くの疑問の声が上がりました。
こうした”現場の壁”に対して、私はAsana導入の意義を繰り返し丁寧に説明しました。さらに、疑問を持っているメンバーの目の前で、実際の業務をAsanaに落とし込み、業務フローの変化を実感してもらう取り組みを続けました。

壁を突破した瞬間
(ファシリテーター)立山氏:皆様がお話ししてくれたようにDXには壁が付き物です。皆様の中で「DXの壁を突破した」と感じた瞬間はありましたか?

村岡氏:私の場合、1部門が使っていたツールが全社に広がったときに突破を感じました。また、Asanaを使っているメンバーが「他のプロジェクトにも使える」などと声を挙げてくれたときも同様です。このような声があったからこそAsanaの意義が情シスや経営層に伝わったと感じます。

渡邊氏:先ほど述べた「数多あるツールの中でなぜAsanaを選ぶのかという点を明確にすること」「全担当者にとって使いやすいツールかどうかを説明すること」という2つの壁を突破するために、全社説明会を実施しました。
その際、役員の1人からポジティブな内容が記載されたフィードバックを全社メールでもらうことができたのです。そこで「Asanaってどんなツール?」という声が一気に増えました。このタイミングを逃すべきではないと考え、私はAsanaの担当者とともに部門ごとに活用説明会を実施し、現場の担当者にAsanaの意義を伝えるために、相談・ヒアリング・プロトタイプ制作・説明・サポートの工程を繰り返しました。
こうした取り組みをきっかけとして15チーム以上がAsanaを導入し、このときに壁の突破を実感しました。振り返って思うのは、導入を進める上で社内の口コミは非常に高い効果を発揮するということです。

原田氏:私が壁の突破を実感したタイミングは2つあります。
1つ目は、Asanaをフォローアップした前後2週間で、プロジェクト作成数が41%増加したときです。この数字は、単なるツールの利用拡大だけではなく、業務が実際に効率化されたという実感が現場に広がった証だと感じています。
2つ目は、開発部門のDX担当部署が明確になり、そこに異動できたときです。これにより、現場からのボトムアップ提案だったDX活動を、自ら推進できる立場になりました。製薬業界は、製剤開発段階のDXはまだ成熟しておらず、当初は理解や共感を得るのが難しい状況でした。そうした中で地道にDXの提案を続けることで、少しずつ共感者が増え、個人単位・チーム単位の改善が課や本部へと広がっていきました。この経験から、DXをボトムアップで進めるには、小さな納得や共感を積み重ねて広げることが重要だと感じています。

当事者だからこそ言える話
村岡氏:新しいツールを使うためには仕事に組み込まなければならないと感じました。当社の場合、Asanaを最初に使ったのはCADチームが設計者から依頼を受けてCADの業務をアウトプットするフローです。私は、このフローをAsanaでしか受け付けないという状態にしました。その上でAsanaに関する説明会を繰り返したのです。
その結果、依頼する側もフローに沿って依頼するだけで済むため、すぐに便利さを実感できました。また、依頼の見える化に寄与した点も導入を促進したと感じます。
「従来のフローを維持したい」という意見もありましたが、エラーが発生した際に履歴を追いやすかったり、各業務を実施したメンバーも見えやすかったりして、担当者にAsanaの便利さが徐々に伝わっていきました。
新しいツールをボトムアップで使い始めるためには、事前の仕掛けづくりが重要だと感じます。そして、いざ使い始めると便利さを実感でき、ツールが定着していくのです。
渡邊氏:私からはDXを推進することで得られたことをお伝えします。1つは、DX推進の過程でさまざまな部署の方と関わることができ、コネクションが増えました。もう1つは、Asanaの推進によりチームを管理する立場にあるメンバーのさまざまなスキルが伸びたことです。
具体的には、Asanaについて、ヒアリング、システム化、実装、共有というプロセスを進める中で次のようなスキルが向上しました。
- ユーザーと折衝する能力
- 構造化する能力
- 実際に作る能力
- 事例化して社内向けにプロモーションする能力
原田氏:私は、提案者とトップの間で「DX計画の目的」について共通理解を築くことの重要性を強く感じました。DXを進めるにあたり、ツールの導入やAIの活用そのものが先行しますが、それらはあくまで手段であり、目的ではありません。
失敗談として、旧部署に所属していた頃、「タレントマーケットプレイス(従業員のスキルや経験をもとに、従業員とプロジェクトをマッチングする仕組み)」の実現を目指し、あるツールを選定・提案したときの経験があります。当時はPoC(概念実証)が不十分だったことに加え、ツールを業務に落とし込む過程で管理職7名の認識が徐々にずれていく事態が発生。さらに、組織改編により管理職のメンバーが入れ替わり、「ツールを使用して実現する目的」が曖昧になってしまったのです。
結果として、ツールの導入自体は成功しましたが、「何に使うかを後から考える」という本末転倒な状況に陥ってしまいました。
この経験を通じて、トップ層との目的のすり合わせは不可欠だと痛感しました。特に、ボトムアップでDXを進める場合、トップ層の後ろ盾があることで、現場も安心して取り組みを前進させることができます。
DXは「ツールを入れること」ではなく、「業務や組織の在り方を変えること」。そのためには、目的を共有し、現場とトップ層が同じ方向を向くことが何よりも大切だと感じています。

これから取り組む方へのアドバイス

村岡氏:当社はDXの一環としてAsanaを導入しましたが、今後も会社全体として最適なツールを検討し続ける必要があると考えています。Asanaは進化のスピードが早いため、このような進化を追いかける体制の構築も重要です。

渡邊氏:当社もAsanaを使うことで業務を効率化できる実感が湧きました。その上でAsanaをより使いこなすために、魅力を伝え続け、使用するハードルを下げる取り組みを繰り返していきます。DXのためには地道な取り組みが大切です。

原田氏:DXを推進するうえで重要なのは、「目的はツールの導入ではない」という視点です。また、DXのための文化醸成も大切です。実際、ツールの導入と比較して文化醸成(企業変革)は15倍重要だとも言われています。そのため、トップ層を説得するのみならず、導入後には一人ひとりが納得し、前向きに使えるよう働きかけることが不可欠です。また、DXを進める際は、社内の各レイヤーが「何を望んでいるか」を考えながら提案する必要があります。
総じて、DXの成功はツールの有無ではなく、組織全体の変革をいかに実現できるかにかかっています。
まとめ

本記事では、リーダーズパネルディスカッション「AIの受け入れと働き方の現在地」およびチャンピオンズパネルディスカッション「現場・ミドルからのチェンジ・マネジメント」の内容を紹介しました。
昨今は各企業でDXが進み、AIを日常的に使用する環境が整ってきています。その中でリーダーはAIエージェントの導入に焦点を当てていることがわかりました。AIエージェントは、RPAなどの従来の技術では実現できなかったレベルで業務プロセスに変革を起こすことができるツールです。
一方、チャンピオン(DXの旗振り役)は、担当者に納得してもらえるツールの導入に注力しています。そのためには、特定のツールを選定する意義、ツールの導入によって発生する具体的な成果を伝え続ける必要があるようです。
また、リーダーとチャンピオンのどちらもDXやAI導入のためにはトップダウンとボトムアップの両輪が重要だという点で意見が一致していました。本記事でお伝えした内容を参考に、自社に合った進め方を見つけることができると、DXやAI導入の取り組みが加速し、各施策が定着するでしょう。
- カテゴリ:
- 働き方改革