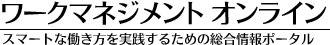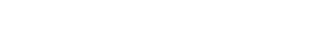属人化からの脱却で年間200時間削減。東光電気工事がAsanaで実現した「現場第一主義」のDX
|
■企業情報
東光電気工事株式会社 ■従業員数 ■取材対応者 DX推進部部長 川田 康博氏 DX推進部 DX推進課 課長 越谷 健氏 神奈川支社 工事管理部 部長 松本 崇氏 |
■導入効果
|
 東光電気工事株式会社 DX推進部 部長 川田 康博氏(左)
東光電気工事株式会社 DX推進部 部長 川田 康博氏(左)
東光電気工事株式会社 DX推進部 DX推進課 課長 越谷 健氏(中央)
東光電気工事株式会社 神奈川支社 工事管理部 部長 松本 崇氏(右)
東光電気工事株式会社(以下、東光電気工事)は、ビルの電気設備や電力インフラ関連の電気工事を担う総合電気設備企業として、全国に広がる支社・現場を横断した業務基盤の強化に取り組んできました。属人化しやすい建設業務において、いかに情報共有とプロセス標準化を実現するか──同社がその解決策として選んだのがワークマネジメントソリューション「Asana」です。
全社導入を経て、現在は「AI Studio」の活用も進み、AIによる業務効率化と知見の蓄積が本格化しています。Asana導入の経緯とその成果、そして今後の展望について、同社 DX推進部 部長 川田 康博 氏、DX推進部 DX推進課 課長 越谷 健 氏、神奈川支社 工事管理部 部長 松本 崇 氏にお話を伺いました。
「良心的な電気工事」を支えて100年
DXに注力し、時代とともに進化する現場力
東光電気工事は1923年の創業以来、人々の暮らしと社会のインフラを支え続けてきました。全国で事業を展開する同社は、ビルなどの屋内設備の配線を担う「内線工事」を主軸としながら、鉄塔での架線をはじめとした「外線工事」、さらに再生可能エネルギー事業や空調衛生設備事業、海外事業などにも力を入れています。
そんな同社では、安全で高品質な建物を提供するために、DX(デジタルトランスフォーメーション)を経営戦略の柱として位置づけています。業務の見える化と標準化によって、より高い生産性や業務効率を実現し、企業価値の向上を目指しているのです。
同社のDXの推進役である川田氏は「単なるIT化ではなく、現場で本当に使えるDXこそが重要です」と強調します。
越谷氏もこう続けます。「当社のように工事部門が多くを占める組織では、現場第一の考え方が根付いています。だからこそ、私たちミドルオフィスが現場の力になれるように、役立つソリューションを提供することが求められるのです」
建設業に迫る業務変革の波
従来型の働き方ではいずれ限界に
少子高齢化や担い手不足が深刻化する中、建設業界ではいわゆる「2024年問題」※に象徴される働き方改革の推進と生産性向上の両立が強く求められています。
東光電気工事においても、こうした課題に加えて、工事規模の大型化や案件数の増加などもあり、従来のような属人的なマネジメント手法では対応が難しくなっていました。「現場の進捗や課題を本社や支社が把握したくても、報告の形式や粒度が担当者によってまちまちで、情報の標準化ができていませんでした」(川田氏)
業務の属人化は、リソース配分の難しさにもつながっていました。繁忙現場への応援要員を配置する際も、誰がどれだけの業務負荷を抱えているかが見えづらく、結果的に適切な支援が遅れることもあったとのことです。
 東光電気工事株式会社 DX推進部 部長 川田 康博氏
東光電気工事株式会社 DX推進部 部長 川田 康博氏
こうした課題を解決するべく同社が注目したのが”ミドルオフィスと現場をつなぐ仕組み”です。「建設業は“職人技”の世界です。その人さえ良ければ回ってしまう面があり、業務が属人化しやすい。だからこそ、1つひとつのタスクに対して関連するコミュニケーションが紐づけられ、業務の透明性を向上させる仕組みが必要だと考えました」と越谷氏は振り返ります。
※ 2024年問題 働き方改革関連法により適用された「時間外労働の上限規制」を起因とする、工期の遅延、労働力不足の深刻化、コスト増加などの問題。
「全員が同じ基盤で働ける」ことを重視
新たなソリューションの導入に際し同社では、現場・本社・支社といった異なる拠点が同じ基盤で業務を進められるようにし、全社的な業務プロセス変革の起点となることを求めました。
 東光電気工事株式会社 DX推進部 DX推進課 課長 越谷 健氏
東光電気工事株式会社 DX推進部 DX推進課 課長 越谷 健氏
社内で既に利用経験があったり、国内外で導入実績があったりする他のタスク管理ツールも候補に挙がり、比較検討が行われました。しかし「UIが複雑で現場にはなじまない」「拡張性に限界がある」といった点が課題となり、誰もが日常的に使える仕組みとしては十分ではなかったといいます。「プロジェクト管理ツールは管理者が使いこなすだけでは意味がありません。全員が使い、現場の声をリアルタイムに反映できる環境こそが不可欠でした」(越谷氏)
そこで浮上したのがAsanaでした。チーム全員が自由にタスクを追加・変更でき、プロジェクトを横断的に管理できる柔軟性を備えている点は、「ワークマネジメントツール」であるAsanaならではの特長です。
「Asanaは『現場とミドルオフィスをつなぐ仕組みの実現』という目的を達成可能だと確信できた唯一のソリューションです。経営層に全社導入を打診する際にも、最も説得力のある要素になったと思います」(越谷氏)
ミドルオフィスと現場をつなぐ“横串”の強みが評価軸に
Asanaの選定理由のひとつに、スケジュール管理のしやすさがありました。ガントチャートやタイムラインを簡単に生成できるような機能は他のツールにはあまりなく、リストから直接スケジュールを作れる点が大きな魅力となったのです。さらに、タスク管理とコミュニケーションを同じプラットフォーム上で完結できる拡張性も評価ポイントでした。
また、同社では2024年4月に本社に工事管理部が設けられ、ミドルオフィスとしてAsanaを用いた業務連携を検討していました。そこでの命題は、現場支援に関する情報を可視化して、その後の打ち手を考えることです。
「そこで、Asanaのマルチフォームやダッシュボード機能を活用すれば、図面作成や見積作成といったミドルオフィス業務を横断的に可視化できるようになると考えました。現場プロジェクトごとそれぞれ管理していた情報を、タグ付けやラベル機能で横串に整理できるのはAsanaならではだと思います。さらにBIツールとの連携による工数管理も可能となり、経営判断に役立つデータ基盤へとつなげることができます」(越谷氏)
段階的なスケール拡大とインフルエンサーの活躍
Asanaの全社導入は、段階的なプロセスを踏むことで確実な定着を図っていきました。2024年7月には3つの支社内で200アカウントでのトライアルを実施し、工事プロジェクトを中心に運用検証を進めました。現場担当者やミドルオフィスの社員が実際に利用し、改善点を洗い出すと同時に、テンプレートやルール作りを検討することで基盤を整えていったのです。
この運用検証において大きな存在感を示したのが神奈川支社です。松本氏は「支社内にAsanaに詳しい社員がいたこともあり、現場からの依頼業務をどのように受け取って履歴を残すか、という観点から導入を検討しました」と当時を振り返ります。
その後、2024年9月には300アカウントに拡大し、本格運用をスタート。新築工事向けのテンプレートが整備されたことで、非定型業務がタスクとして整理され、標準化の効果が見え始めました。さらに同年10月には100アカウントを追加し、計400アカウントへと展開。
順調に展開していけた背景には、神奈川支社と東京西支社に存在した強力な“インフルエンサー”が現場の利用を牽引しました。
越谷氏は「Asanaを積極的に活用し、さらにナレッジも共有していこうとする動きがあり、特に神奈川支社については『あの支社ではツールをうまく使って業務を効率化できている』という評判が全社的に広まりました」と振り返ります。
神奈川支社のように先行して成功事例が出たことにより、他の支社からも「なぜ自分たちの支社は後だったのか。自分たちもAsanaを使いたい」という声が出るようになりました。こうした現場の熱量が経営層にも伝わり、2025年2月には一気に全社員へと広がります。最終的に1,500アカウントを展開し、同社は「トココラ(Toko collaborationの略)」と名付けた全社協業プロジェクトとして本格導入に踏み切りました。
ベンダーの伴走と経営層の後押しが全社浸透を加速
全社導入を加速させたもう1つの要因が、Asanaの担当者による密なサポートでした。
川田氏はその効果を次のように強調します。「どんなにサービス自体が良いものでも、寄り添う姿勢がなければ選びません。Asanaは導入初期から担当者が日々のタスク作成方法や運用ルールの整備を手厚く支援してくれて、現場社員が安心して利用を始められる環境を整えるのに寄与しました」
越谷氏も「毎日のタスクの作り方を丁寧に見てもらえたことで、導入に対する不安が和らぎました。サポートの手厚さはとても心強かったです」と続けます。
経営層からの後押しも決定的でした。「役員から『全員でいっせいに使いはじめたほうがいいのではないか。不公平感をなくし、機会を平等に与えるべきだ』と強い提言がありました。400アカウントの時点で一気に全社展開したのは私自身も驚きました」(川田氏)
 東光電気工事株式会社 神奈川支社 工事管理部 部長 松本 崇氏
東光電気工事株式会社 神奈川支社 工事管理部 部長 松本 崇氏
さらに、中期経営計画をAsanaのゴール機能に反映させ、役員自身が積極的に操作する姿勢を見せたことで、社員の納得感も高まりました。また、実際にAsanaを使用した経営層から「意外と簡単に使える」という声も出たことが、全社浸透に大きく寄与したといいます。
全社員が日常業務で活用する「毎日のタスク」として浸透
現在、東光電気工事では全部門に加え、協力会社社員や派遣社員も含めてAsanaを利用しています。基本となるのは、「毎日のタスク」を全社員が入力し、それを基点として工数の可視化やカレンダービューでのスケジュール管理を行う作業です。入力された情報は自動的にガントチャートに反映され、進捗管理や計画との差異確認が容易になりました。
松本氏は「神奈川支社の工事管理部として、まずは現場からの依頼をタスクとして入力してもらい、進捗管理できるようにしました。フォームを用いることで、現場側は最小限の入力で依頼を出せるようになり、ミドルオフィスとの連携が格段に効率化されました」と話します。
このように、全国に点在する現場とオフィスの距離を埋めるコミュニケーション基盤としても、Asanaは日常業務に欠かせない存在となっているのです。
さらに、誰がいつどの程度の業務を抱えているかを「ワークロード」機能で把握し、画面上で業務の振り分けを行うことで、業務量の平準化も進んでいます。
AI Studioでさらに進化するワークマネジメント
同社が特に注力しているのが、Asanaの「AI Studio」を活用した業務プロセスの高度化です。越谷氏は「ミドルオフィスへの申請に対し、AIが担当者のワークロードやスキルを加味して推薦してくれる仕組みを導入しています」と説明します。
また、中期経営計画の進行状況もAIで評価し、順調か課題があるかを即座にレポートできる仕組みも整えました。「これまで数時間かけていた報告書作成が、AIの出力をベースにすれば数秒で済むようになり、利用価値は非常に高いです」と越谷氏は手応えを示します。
川田氏も「毎日のタスクや経営の進捗状況をプロンプト入力だけでサマリー表示でき、そこから詳細にブレイクダウンできます。従来のようにデータを一件ずつ集計する必要がなくなり、大幅な効率化につながっています」と評価します。
松本氏は「誰がどれだけの業務を抱えているか、その繁忙度合いをAIが補助的に把握することで、今後さらに拡大すればAIの役割はますます重要になるでしょう」と展望を述べます。
リモート環境からでも依頼や進捗管理ができるAsanaは、分散した現場を抱える同社にとって不可欠な業務基盤となりつつあるのです。
大幅な工数削減と全社ペーパーレス化を実現
AIを活用したプロジェクト進捗の可視化によって、中期経営計画の進捗レポート作成も効率化されています。従来30分かかっていたポートフォリオレポートはわずか10分で作成可能となり、25分短縮×500回=およそ200時間の削減を実現しました。
また、Asana導入によってペーパーレス化も進みました。これまで多くの支社や部署でExcelを用いて管理していたスケジュール会議は、紙に印刷した資料を前提としていました。しかし現在はAsanaに入力したデータをそのままモニターに映して議論できるようになり、年間で約3,000枚に及ぶペーパーの削減につながりました。
「社長や役員クラスも含め、11支社がほぼAsanaで管理されるようになり、ペーパー資料は大幅に減りました」(越谷氏)
Asanaが組織全体の“変革エンジン”に
一方、定性的な効果も数多く挙がっています。越谷氏は「Asanaは単なる便利なツールというよりも、業務そのものの仕組みを変える契機になりました」と強調します。
東京西支社での導入初期には、工事発生から見積もり、決定後の実行予算書作成までの流れをAsanaで管理し、バックオフィスが担う仕組みを構築しました。これにより、従来属人化していた業務がテンプレート化され、全社に横展開されつつあります。
川田氏も「ミドルオフィス側での実行予算書の作成や入力で不明点があれば、フロントオフィスに確認しながら進めることができます。Asanaを通じて双方の業務理解が深まり、工事に紐づいたやり取りがよりスムーズになっています」と評価します。
松本氏はエンドユーザーの立場からの変化を次のように述べます。「Excel管理では期日を過ぎても気づかないことが多かったですが、Asanaに入力して期日を設定すれば自動的にアラートが出ます。担当者が早い段階で気づけるので、工事が滞ることなく安定して進められるようになるはずです。今期の工事スケジュールを入れて試している最中ですが、今年度の成果が楽しみです」
このように、Asanaの導入は定量的な時間削減やペーパーレス化にとどまらず、業務プロセスの再設計や相互理解の深化といった質的な変革をもたらしています。
現場発の進化を次のステージへ──業界全体への波及も視野に
Asanaの全社展開を果たした東光電気工事は、次なる1年を見据えた新たな挑戦に踏み出しています。
まず注力するのは、現場から個人タスクへとシームレスにつながる仕組みづくりです。新築工事のマイルストーンを起点に、そこから派生するタスクを共有して個人業務への落とし込みと組織への展開をスムーズに行えるようにすることを目指しています。「入口はすべてAsanaから」とすることで、個の活動を組織全体へと波及させ、真の働き方改革につなげようとしているのです。
次に取り組むのは、テンプレートのさらなる拡大です。川田氏は「実行予算作成業務に加え、見積書作成業務もテンプレート化して全社展開を始めています。これによりフロントオフィスとミドルオフィスの連携を、より強固にできると考えています」と話します。
管理帳票の多くをExcelからAsanaへ移行することにより、現場の搬入予定や作業員の追加といった情報もリアルタイムで共有できる環境を整えようとしているのです。
また、現場との連携強化も大きなテーマです。越谷氏は「現在はオフィス間の橋渡しとしてAsanaを活用していますが、次のステップは現場でどれだけ効果を感じてもらえるかです。作業完了報告などをAsanaに埋め込み、1分1秒のさらなる効率化につなげたいですね」と意欲を示します。
松本氏も「ホテルのように何十フロアもある現場では、どこが終わったかをチェックするだけでも大きな手間です。AsanaとBIツールを連携させれば、労働時間の削減に直結するでしょう」と期待を寄せます。
さらに、AI Studioへの期待も高まっています。タスクの所要時間推測や最適な担当者の自動割り当て、期日の自動設定といった機能は、現場の負担軽減と効率化に直結するからです。
越谷氏は、AI活用によるさらなる業務改革に意欲を示し「今後は、担当者を推薦するためにワークロードやスキルを割り振る、AIを組み込んだテンプレートを全社に配布する予定です」と話します。
今後は、システムやBIツールとのデータ連携を強化し、経営判断に直結する仕組みを整えると同時に、施工要領書や施工計画書といったナレッジをAIで解析・共有する仕組みも構想しています。安全や品質管理への適用拡大も視野に入れ、現場のデジタル基盤を一層強化していく考えです。
川田氏は「建設業界でAsanaが広がれば、さらに連携の幅が広がるはずです。特にスケジュール管理は建設業で最も重要な領域。多様なファイル形式やPDF出力への対応拡充にも期待しています」と語ります。
東光電気工事のAsanaを活用した取り組みは、単なる自社のDX推進にとどまらず、業界全体の変革に波及する可能性を秘めています。現場起点のデジタル活用を積み重ねることで、建設業界が抱える構造的課題に挑み続ける姿勢が示されているのです。
- カテゴリ:
- Asanaのヒント