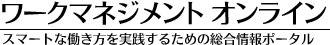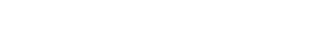マルチタスクとは? メリットや得意な人の特徴、やり方、管理ツールについて解説
複数の仕事を同時にこなしていく「マルチタスク」は、ビジネスシーンにおいて、ごく一般的に行われています。しかし、マルチタスクが得意な人もいれば、苦手な人もいます。この記事では、マルチタスクのメリットとデメリットを解説するとともに、得意な人とできない人の特徴、マルチタスクを成功させるやり方を取り上げます。

マルチタスクとは?
マルチタスクとは、「multi(複数の)」と「task(仕事、作業)」を組み合わせた言葉です。複数の作業を同時進行させることを意味します。もともとはIT用語として使われており、コンピュータで複数の情報を同時に処理することをマルチタスクと呼んでいました。近年ではビジネス用語として使われるのが一般的になっています。ビジネスシーンでは、電話対応をしながらパソコンにデータを入力する、議論に参加しながら議事録を作成するなど、特に意識せずマルチタスクを行っている方もいるはずです。
シングルタスクとの違い
シングルタスクはマルチタスクの対義語です。ひとつの作業に集中して取り組み、それを完了させてから次の作業に取りかかることを意味します。両者を比較すると次のようになります。
- シングルタスク:作業をひとつずつこなすこと
- マルチタスク:複数の作業を同時進行させること
シングルタスクが向いている場合もあれば、マルチタスクが向いている場合もあり、どちらかが優れているというわけではありません。マルチタスクは業務を効率化して生産性が上がると考えられがちですが、業務の内容によってはシングルタスクのほうが生産性の上がるケースもあります。
仕事でのマルチタスク実行例
例えば、優先度の高いものから順に、タスクA、タスクB、タスクCの作業があるとします。マルチタスクを実行すると、タスクAのロスタイムを利用してタスクBの進捗を確認し、さらにすぐ終わるタスクCにも着手するというように、複数のタスクを同時進行させられます。
仕事でのマルチタスクの実行例には次のようなものがあります。
- 複数のプロジェクトを同時に進める
- 顧客と交渉をしながら、社内稟議にかける
- 自分の商談を進めながら、部下のマネジメントをする
- 見積書を作成しながら企画書を作成する
- クレーム対応を行いながら、戦略会議を企画する
マルチタスクのメリット
マルチタスクには、同時に複数の仕事をできる、仕事全体を把握しやすい、コミュニケーションに役立つという3つのメリットがあります。複数の仕事を同時にできる
マルチタスクは、限られた時間内に複数のタスクを実行でき、効率よくタスク処理を行える点がメリットです。複数のタスクを同時に処理していくことで、業務の停滞を防げます。シングルタスクではほかの仕事が止まってしまい業務が停滞する恐れがありますが、マルチタスクならそのような心配はいりません。性質の似ているタスクや期日の近いタスクは、マルチタスクを実行することでより早く完了させられます。
また、普段からマルチタスクを心がけていると、すべての業務の進捗状況をある程度把握できるため、イレギュラーな業務が入った場合でも対応しやすくなるのもメリットです。
業務の全体像を把握しやすい
マルチタスクを実行するには、抱えているすべてのタスクの内容や納期の把握が不可欠です。自分が担当する業務の上流工程から下流工程までの全体を把握することによって、工程内の問題や課題を認識できます。問題があればリスクヘッジできるようになるため、万が一トラブルが起こった場合でも、重要度や緊急度にあわせて早急に対応可能です。コミュニケーションに役立つ
マルチタスクをこなすことは、良好なコミュニケーションを取るために有用です。マルチタスクに慣れていると、報告や指示、共有などもすんなりと進められるようになります。
複数の業務を抱えているということは、それに伴ってコミュニケーションを取るべき人の数も増えているということです。それらの人たちと協調しながら業務を進めることで、業務における「顔見知り」の人が増えていき、次の業務にもその人脈を生かせます。
また、常にマルチタスクをこなしている人は顔が広く、周囲からの相談を受ける機会も増えていきます。それによって、まだ表面化していない新たな課題点の収集も可能になります。
マルチタスクのデメリット
マルチタスクにはメリットがある一方で、生産性が低下する、キャパシティオーバーになりやすい、脳疲労が蓄積する、ミスが起こりやすいなどのデメリットもあります。生産性が低下する
マルチタスクを実行することで生産性が低下するケースがあります。
マルチタスクでは、タスクを切り替える際にロスタイムが発生する傾向にあります。例えば、「タスクAはどこまで進んでいたか」「タスクBには何が必要だっただろうか」などをその都度振り返る時間です。そのため、タスクの切り替えがうまくできないとトータルで見た際に作業効率が落ちてしまい、結果的にはシングルタスクのほうが早い場合があります。マルチタスクで必ずしも生産性が上がるとは限らない点に注意しましょう。
キャパシティオーバーになりやすい
キャパシティオーバーを招きやすいのも、マルチタスクのデメリットです。
シングルタスクであれば、そのタスクさえ期限内に終わらせればよいため、スケジュール管理やリスク管理がシンプルです。
しかし、マルチタスクでは、すべてのスケジュールやリスクを管理しながら進めなければなりません。「クレームが発生したタスクAの対応に追われて、タスクB・タスクCに手を付けられていない」「タスクAの修正が必要になったので、タスクB・タスクCにも変更を加えなければならない」など、ひとつの作業だけでは起きなかったトラブルが起きる可能性もあります。
期日が近いタスクばかりを抱えている場合は、ひとつの作業が遅れると、ほかの作業にも影響を及ぼします。また、普段は問題なくこなせる量のタスクだったとしても、体調不良などの予期せぬ事態が起きたとき、すべてのタスクがストップしてしまうリスクもあります。
脳疲労が蓄積する
マルチタスクを実行すると、脳に疲労が溜まるというデメリットもあります。違うタスクに取りかかる度に頭を切り替える「タスクスイッチング」に、エネルギーがかかるのは想像に難くありません。そもそも、人間の脳はひとつのことをするようにできており、マルチタスクには不向きだという研究結果も出ています。
スマートフォンやタブレットの普及によって、複数のデバイスを同時に使う機会が増えました。利便性が高まった一方で、複数のデジタルデバイスの同時使用は脳に悪影響を及ぼすのではないかという考えもあり、調査が行われている段階です。マルチタスクによる脳への悪影響が明らかになっている調査として、次の2つを紹介します。
①マサチューセッツ工科大学の脳神経科学者であるEarl Miller教授の調査(記事原題:Multitasking Is Killing Your Brain)によると、タスクを切り替える度に「認知コスト」がかかり、常時タスクを切り替えることが脳に悪い影響を及ぼすと明らかにされています。Earl Miller教授は、一見マルチタスクをしているようでも、「実際はひとつのタスクから次のタスクに切り替えているだけ」とも述べています。
参照元:Multitasking Is Killing Your Brain
②サイエンス誌によるリポート(リポート原題:Divided Representation of Concurrent Goals in the Human Frontal Lobes)では、人間の脳はデュアルタスク(二重課題)が限界ということが明らかにされています。この調査では、2つのタスクを処理するとき、人間の脳は左右の前頭葉が自動的に処理機能を2つに分割しますが、3つ以上のタスクになると、前頭葉の能力は損なわれることがわかりました。つまり、2つのタスクは同時に処理できても、3つ以上のタスクは脳の機能的に同時に処理できないということです。
参照元:Divided Representation of Concurrent Goals in the Human Frontal Lobes
焦りによるミスが起こりやすい
マルチタスクを順調にこなしている間はよいものの、予期せぬトラブルなどによって作業が滞ったときに、焦りから普段なら考えられないようなミスが起きることがあります。期限が迫っていて、「必ず終わらせなければ」という強いプレッシャーが生じるとなおさらです。
トラブルが起こると焦ったり慌てたりし、トラブルへの対処の難易度が高いほどイライラもつのります。イライラすることで判断力が低下し、それによってさらに次のミスまで誘発してしまい、結果的に信頼関係に傷が入ってしまう、という悪循環に陥ってしまうことは珍しくありません。
すべてのトラブルを予想するのは困難ですが、余裕を持ったスケジュールで動くなどの対策は必須です。
マルチタスクが得意な人の特徴
マルチタスクを得意とする人がいる一方で、苦手意識を持つ人もいます。双方それぞれにどのような特徴があるのか、まずは得意な人の特徴を紹介します。情報の整理整頓が得意な人
スケジュール管理など情報の整理整頓に長けている人は、マルチタスクに向いています。情報の整理整頓が得意な人には、スケジュールを瞬時に把握する能力や、情報を的確に活用する能力があります。そのため、進捗状況や納期、関係者の情報などをしっかりと整理し、プロジェクトを管理できます。優先順位を決められる人
マルチタスクは、タスクの重要度や緊急度を見極め、的確な優先順位をつける必要があります。納期が迫っているプロジェクトや重要な仕事は優先的に処理していかなくてはならず、別の仕事を依頼された場合はすぐに優先順位をつけ直す必要もあります。
優先順位を決められる人は、多くの仕事が舞い込んできた場合でも動じず、適切な順番でタスクを行えるため、効率的に業務を進められます。
切り替えが早い人
マルチタスクは、短時間でタスクを切り替えて処理していく必要があるため、切り替えの早さは重要です。タスクが切り替わっても集中力を切らさずにいられる方は、マルチタスクに向いています。
また、感情面でも同様です。ミスをしてしまった場合でも、落ち込んだ気持ちを引きずらず次のタスクに切り替えられるなど、感情の切り替えがうまくできる人は、マルチタスクも得意な傾向があります。
マルチタスクができない人の特徴
こだわりが強い人や完璧主義の人は、マルチタスクを得意としません。ただし、向き・不向きが大きく関わっているため、「マルチタスクができない=仕事ができない」という考えは大きな間違いです。こだわりが強い人
こだわりが強い人は、物事をよい意味で「適当」にできず、タスクの中断がストレスになります。そのため、タスクをうまく切り替えられない可能性があります。複数のタスクを抱えてしまうと、タスクの仕上がりに納得いかず、期日に間に合わないという事態が起こりかねません。
また、こだわりが強い人は集中力が高く、深く考える傾向にあります。そのため、シングルタスクのほうが実力を発揮しやすく、成果にもつながります。
完璧主義な人
「ミスしたくない」という意識が強い、完璧主義な人もマルチタスクに不向きです。いわゆる職人気質、アーティスト気質の人が該当します。完璧主義な人は慎重に仕事を進めたいと考える傾向があり、複数のタスクを抱えると次のタスクに切り替わってからも前のタスクのことを考え続けてしまいます。結果的に、集中力が途切れてしまい、各タスクの完成度も低下する恐れがあります。
また、完璧主義な人は妥協したくないという気持ちから、強いプレッシャーを感じることが多々あります。体調を崩してでもすべてのタスクをやり遂げようと無理をしてしまうケースも少なくありません。ただし、ミスは少ないため、失敗が許されない重要なタスクやシングルタスクでは実力を発揮します。
マルチタスクを成功させる3つのやり方
マルチタスクを成功させるための3つの方法について、それぞれの概要や手順を解説します。1. 「1×10×1」システムを取り入れる
「1×10×1」システムとは、1分以内に終わる仕事、10分以内に終わる仕事、1時間以内に終わる仕事の3つに分類し、順に終わらせていく方法です。例えば、メールの返信、会議への出席依頼など1分以内に終わる仕事を先に済ませ、資料や議事録の作成・チェックなど10分以内に終わる仕事を行います。1時間ほど必要なタスクは、遅くてもその週のうちに作業時間を確保します。
この方法は、短時間で終わる仕事から次々に処理していくため、着実にタスクを消化でき、タスクが山積みになるのを回避できます。シングルタスクのようにひとつの作業に集中できるうえ、マルチタスクのように複数のタスクを完了させられるメリットもあります。
2. パーキングロット思考を意識する
パーキングロットとは、ビジネスシーンにおいて、優先度の低い問題を一時的に保留・蓄積しておくときに使われる言葉です。会議やミーティング中に、本題ではない緊急性の少ないアイディアを蓄積しておく際にも用いられます。付箋に書いて箱に入れておく、インターネット上のツールで管理するなど、やり方はさまざまです。
パーキングロット思考によって業務の本筋から逸れにくくなり、スムーズにマルチタスクを実行できます。また、ほかの仕事を頼まれた場合でも、一旦保留することによって、今行っているタスクに集中できます。無条件に保留するのではなく、緊急性がないかどうか必ず確認しましょう。
3. タスク管理ツールを導入する
タスク管理ツールを導入すると、各タスクの内容や期日、進捗状況などを可視化でき、タスクの抜け漏れが少なくなります。
自分の抱えるタスクを管理するほか、複数のメンバーで進めるプロジェクトの管理にも有効です。プロジェクトではほかのメンバーの進捗状況がわかりにくいですが、タスク管理ツールを導入すれば各々の進捗状況を確認でき、今何をすればよいかがすぐにわかります。
また、自分やチームメンバーの状況が明確になり、周りにも相談しやすくなるため、キャパシティオーバーになることもなくなります。上司も状況を見て仕事を割り当てるなど、スムーズに部下をフォローできます。新たなタスクが増えてタスクの優先順位を変更した場合や、プロジェクト全体に変更があった場合でも、タスク管理ツールがあればすぐに対応可能です。
マルチタスクの管理に!ワークマネジメントツール「Asana(アサナ)」
タスク管理ツールを導入するなら、「Asana」がおすすめです。おすすめする理由は、次の3つです。
- 実績:世界200の国と地域、147,000社以上で導入
- 機能性:チームやプロジェクト全体のタスク管理が可能
- システム連携:Slackなどを始めとした各種ツールと連携可能
マルチタスクをサポートするツールは数多くありますが、「Asana」は世界各国の企業で多くの導入実績を誇ります。
また、機能性に優れており、自分自身はもちろん、チームやプロジェクト全体のタスク管理が可能です。プロジェクトの進捗状況をドーナツチャートで可視化する、プロジェクトの収益状況をグラフで確認するなど、リアルタイムで情報を一元管理できます。
さらに、Gmail、Microsoft Teams、Slackなど、さまざまなアプリケーションとの連携も可能です。関係する情報をひとつのプラットフォームで管理できるため、過剰な進捗報告をする必要がありません。遅れや滞りのあるタスクもすぐにわかるため、ボトルネックの特定や改善にも役立ちます。
まとめ
マルチタスクには、複数の仕事を同時にできる、コミュニケーションに役立つなどのメリットがあり、業務効率化のために有用です。しかし、こだわりが強い人や完璧主義な人など、マルチタスクに向かない人もいます。無理にマルチタスクを実践するのは、ミスをする恐れがありかえって非効率です。シングルタスクを実践するほか、「Asana」などのタスク管理ツールを使うことをおすすめします。進捗状況など情報を一元管理できるタスク管理ツールなら、突発的なトラブルが発生した場合でも、余裕を持って対応できます。- カテゴリ:
- プロジェクト管理