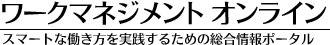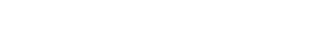プロジェクト計画書とは? 目的、必須となる8つの項目など立て方を解説
プロジェクト計画を進める際には、適切な計画書の作成が大切です。メンバー間やステークホルダーとスムーズに共通認識を持てることで、確実なプロジェクト成功へとつなげられます。 この記事では、プロジェクト計画の概要や必要性、計画書を作成する際のポイント、作成の手順などについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。プロジェクト計画書とは
「プロジェクト計画書」とは、その名のとおりプロジェクトを進めるにあたって作成する計画書のことです。プロジェクトの始動から当初立てた目標達成までの筋書きを書いたものとも捉えられます。
主にプロジェクトマネージャーと呼ばれる担当者が、具体的な内容や進め方、最終的に求める成果物などについて、網羅的に記載するのが一般的です。
プロジェクト計画書がメンバー全員で共有されていれば、途中で何らかのトラブルに巻き込まれても軸がぶれず、どのように修正、改善すればよいのかが明確になります。
そもそもプロジェクト計画とは
プロジェクト計画書の原点となる「プロジェクト計画」とは、プロジェクト開始から完了までのプロセスを示すものです。チームメンバーが目標達成に向けて行うべき業務だけでなく、必要となる資源やタスクの優先順位など、ポイントとなる要素や情報がすべて盛り込まれているのが特徴です。
プロジェクト計画を立てていないと、プロジェクトに携わるメンバーは、何が・いつの時点で・どのように行われるかなどを正しく把握できません。逆に綿密な計画を立てておくことで、プロジェクトメンバー全員が同じ目標に向かって業務を遂行できます。
プロジェクト計画書とプロジェクト憲章の違い
プロジェクト計画と似た意味でよく使われる用語に「プロジェクト憲章(プロジェクトチャーター)」があります。
プロジェクト憲章も、プロジェクトにまつわるさまざまな情報を記している点は同じです。ただ、主にステークホルダーへのプロジェクトの認知や承認を目的とした、いわゆる企画書である点に決定的な違いがあります。また、企画書という性質上、基本的にはプロジェクトが始動する以前に作成されます。プロジェクト計画書ほど、詳細な内容も必要とされません。
一方、プロジェクト計画書はプロジェクトが始動してから、どのように進めていくのかを決め文書化します。
プロジェクト憲章に関する詳細は、ぜひ以下の関連記事もご参照ください。
関連記事はこちら
プロジェクト計画と要件定義の違い
プロジェクトを進める際、「要件定義」も重要なポイントとされます。しかし、プロジェクト計画との違いについて知識があやふやな人は少なくありません。
要件定義は、プロジェクト計画書を前提として、実現したい業務に何が必要なのか要件をまとめる作業を指します。つまり、プロジェクト計画を策定した後に行う段階であり、そもそも実施時のフェーズが異なるものと認識しておきましょう。
要件定義が甘いと、後の工程で計画が破綻するなどの事態を招きかねません。そのため、業務の内容を把握することはもちろん、現在の弱みやハードルになっている点、それをクリアするための対策として技術的・機能的な要件をしっかり考えることが大切です。
プロジェクト計画とプロジェクトスコープの違い
「プロジェクトスコープ」とは、プロジェクトにおいて「すること」と「しないこと」の範囲を指定する作業を指します。つまり、規模や境界を定めることです。
プロジェクトを進める際、あれもこれもとしたいことを詰め込み過ぎると、計画がうまく進まない原因になります。時間や予算には限りがあるため、どこまで取り組むのかを線引きしなければなりません。
中長期的な視点を持ち、プロジェクトを効率よく成功させるためにも、プロジェクト計画の一部としてプロジェクトスコープを明確化しましょう。
プロジェクト計画を立てる目的
プロジェクト推進にあたり計画書を作成する目的としては、2つに大別できます。
まず、「プロジェクト成功の確実性を上げるため」です。 計画が甘い、あるいはまったく計画せずにプロジェクトを始動してしまうと、タスクの抜け漏れが途中で判明したり、メンバーの業務内容が重複したりするなどのトラブルが発生しやすくなります。無駄なコストがかかるほか、計画が思うように進まなくなりかねません。
そのため、最初にプロジェクト範囲から具体的なスケジュール、タスク、期日、担当メンバーの割り振り、成果物などを、プロジェクト計画書で明示しておくことが重要です。
計画書がメンバー間で共有されていれば、急きょ必要なタスクが増えたり、期日が変更されたりした場合にも適切な対応策をメンバー全員で検討しやすくなります。
次に、「社内で情報共有をスムーズに行うため」です。
プロジェクト計画書を作成しておくことで、チームメンバーだけではなく、経営陣や他部署との情報共有がはかどります。最終的なゴールやそのプロセス、責任範囲などの共通認識を持てば、プロジェクトを成功させやすくなるはずです。
また、プロジェクト計画書を作成する目的はほかにもあります。プロジェクトが長期にわたる場合、途中でチームメンバーの入れ替えなどがあるケースも少なくありません。その場合にも、遅滞なくプロジェクト業務を進められるようにするためです。
プロジェクト計画の立て方
プロジェクトを任された場合、どのように計画を立てていけばよいのでしょうか。各企業によって異なるところはあるものの、プロジェクト計画は、以下の7段階で進めるとスムーズです。
1.中長期の目標設定
まず、プロジェクトがめざす中長期的な目標を掲げることが大切です。計画書によってゴールの姿をメンバーが常に確認できるため、軸をぶれさせずに目標達成へ近づけます。
2.成功の評価指標設定
目標達成に向かって業務が順調に進んでいるかどうかを客観的な指標で測れるようにします。たとえばSpecific (具体的)、Measurable (測定可能)、Achievable (達成可能)、Realistic (現実的)、Time-bound (期限がある)の頭文字をとった「SMART」といったフレームワークなどがおすすめです。
3.関係者と役割の明確化
一般的に、プロジェクトにはさまざまな人が関わります。そのため、「直接的な責任者は誰にするのか」「最終の意思決定を下す承認者は誰か」「部門をまたいだプロジェクトの場合、どの部署のどのメンバーに参加してもらうのか」などを決めましょう。
4.予算の設定
プロジェクトにどれだけの予算をかけるのかを決めます。前段でめざす目標や関係者が決まっていれば、おのずと必要な経費も見えやすくなります。計画を立て予算を決めることで、プロジェクトをスピーディに進められるほか、無駄な支出も削減可能です。
5.マイルストーンと成果物に関する具体的な目標設定
マイルストーンとは、プロジェクトを成功させるために欠かせない中間的な目標を指します。期日までにどれだけの成果物ができているのか、進捗確認するための中間目標も設定しましょう。マイルストーンに達すれば、プロジェクトにとってひとつの成果になり得ます。
6.タイムラインとスケジュールの設定
プロジェクトを成功させるためには、全体像が見えるタイムラインやスケジュールを作成することも大切です。その際、まずプロジェクトの取り組みで、何を優先的に実施するのか順位付けしましょう。タスクや順序を定められたら、誰がいつ何をするのか担当者などを決めます。さらにタスクを細分化し、業務の開始日と締め切り日を計画書に落とし込んでいきます。
7.コミュニケーション計画の共有
現時点での進捗状況や今後の予定などを全メンバーが適切に把握できるように、コミュニケーション計画を作成、共有します。
プロジェクトを進めていくなかでは、トラブルの発生もよくあることです。そこで迅速かつ的確にリカバリーするためには、関係者間のコミュニケーションが重要なポイントになります。
プロジェクト計画書を作成するにあたってのポイント
プロジェクト計画書は、いくつかのポイントを押さえて作成することが重要です。ここでは、計画書作成にあたって気を付けたいポイントを3つに分けて解説します。フォーマットを決める
プロジェクト計画は、のちに何らかの事情により変更となる可能性もあります。実際は予定通りに行かないことも多々あるため、その都度修正しなければなりません。ただ、修正する場合、フォーマットが用意されていないと大きな手間がかかります。
フォーマットは、プロジェクト計画書の作成段階から決めておくことがおすすめです。計画を修正するメンバーは、作成メンバーと異なることもあるため、フォーマットが決められていなければ混乱を招きかねません。そのような事態が起こらないよう、事前にフォーマットを決めておきましょう。
図やグラフを用いる
先に述べたように、プロジェクト計画書は、複数の関係者と認識を共有することも目的のひとつです。しかし、多数の関係者が参画するプロジェクトの場合、専門性も多岐にわたるため、専門用語の羅列だとイメージを共有できない可能性があります。計画書は、誰でも視覚的にわかりやすい形での作成が求められます。
そこで、図やグラフを活用して定量的に記載するのがおすすめです。また、図やグラフの作成過程で洗い出されるデータは、プロジェクト計画実現の確実性をさらに押し上げます。確実なデータが図やグラフで示されることで、誰が見ても説得力のある計画書になります。
情報共有を綿密にする
プロジェクト計画書が完成すれば、それで終わりではありません。どのような内容が書かれているのか、あるいはどのように読み進めればよいのかなどを、関係者に周知徹底しましょう。 目的のひとつ「情報共有をスムーズにする」ことも頭に入れ、メンバー全員が同じ認識を持てていることを確認します。プロジェクト計画書の重要な8つの項目
計画書の仕様に決まりはなく、企業やプロジェクト規模によって必要な量もさまざまです。ただ、内容として盛り込むべき項目は主に8つあります。
ここでは、各項目についてわかりやすく解説します。
プロジェクトの目的・目標
最初に、なぜこのプロジェクトを進める必要があるのか、何をめざすのかといった、根本となる「目的」や「目標」を明確に記載しましょう。もし目的があいまいであれば、メンバー間の認識に食い違いが生じ、結果として本来の目標にたどり着けない状況になりかねません。
また、目標を記載する際には、プロジェクト終了後に客観的に評価できるように、定量的な数値を盛り込みます。とくに「QCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)」と呼ばれる生産管理の指標を用いると、より的確に評価できます。
プロジェクトの範囲(スコープ)
次に、プロジェクトをどの業務範囲(スコープ)まで広げて行うかを決めます。業務の一部を対象とするなら、そのシステムの範囲を明確にし、「WBS(work breakdown structure)」と呼ばれる「作業分解構成図」を作成するのがおすすめです。もちろん、部署や担当のように、組織における対象範囲を指定する場合もあります。いずれにせよ、プロジェクトで取り組む範囲がはっきり定まれば、「誰が」「何を」「どこまで」するのかといったタスクを正しく洗い出すことが可能です。
また、複数の部署が参加するようなプロジェクトであっても、業務範囲を明確にすれば自分の部署でやるべきことがよく見えるようになります。複数部署で同じ業務が無駄に重複するリスクを避けられるのもメリットです。
プロジェクトを運営するための体制
プロジェクトはとくに社内のさまざまな部署で連携して進められることが少なくありません。 そのため、始動前に社内の運営体制をしっかりと組むことで、スムーズな活動へつなげられます。どの部署のどのメンバーが参加するのかを取りまとめるとともに、その部署の従業員一人ひとりの役割についてもはっきりさせておくと、目標を達成しやすくなるはずです。
また、社内体制を組むことは、責任範囲の明確化にもつながります。自組織ですべきことが明らかになり、タスク管理がしやすくなったり、伝達ミスが減ったりするメリットも得られます。プロジェクトの規模や社外メンバー参加の有無によっては、利害関係が複雑になる可能性もあるため、最新の状況をいつでも確認できるようにしておくことが重要です。
項目ごとにかかるコスト
プロジェクト範囲が定まれば、次は項目ごとにかかるコストを明らかにします。プロジェクトには予想以上にコストがかかることも少なくありません。あとで「こんなはずではなかった」とあわてないように、抜け漏れなくピックアップしましょう。
たとえば人件費なら、作業時間と作業人数で算出が可能です。また、ソフトウェア費用やハードウェア費用、インフラ費用、ライセンス費用なども確認して記載します。
このように細かく項目ごとに予算を算出しておけば、予算がオーバーした際、どこで超過したのかを素早く確認可能です。ひいてはプロジェクトを早期に実現できる可能性が高まります。
また、プロジェクト終了後に、費用対効果を測るのにも便利です。次のプロジェクトを実施する際には、改善点としてつなげられます。
全体のスケジュール
プロジェクトにかかるコストの見積もりを把握できたら、次は全体のスケジュールを把握しましょう。
プロジェクトのフェーズを大まかに分け、流れがわかるように工程表を作成するのが一般的です。そうすることで、各メンバーはプロジェクトの全体像を頭に入れながら効率よく活動できます。途中の進捗状況を随時確認できるように、先に紹介したマイルストーン(中間目標)も設定しておくのがポイントです。
ただし、プロジェクト計画書には、スケジュール上の細かな実作業まで記載する必要はありません。なぜなら経営層は、現場レベルの詳細なスケジュールまで見ないためです。またメンバーも、全体像がわかるスケジュールのほうがプロジェクトのイメージを掴みやすくなります。最も作業時間がかかりそうなクリティカルパスのみを載せたり、管理指標を記載したりするだけで十分です。
成果物の品質管理
プロジェクトを進めた結果、ソフトウェアやハードウェア開発などで完成した設計書や納品物を「成果物」と呼びます。プロジェクトにおいては、成果物の品質についてもきちんと管理することが必要です。その際、計画通りのものが出来上がっているかを確認するために品質管理の担当者を設定しておくと、管理が行き届きやすくなります。
また、プロジェクトの目標達成度を測るには、品質分類や品質項目、品質指標、目標値などで分類しておくとわかりやすくおすすめです。ただ、定性的な基準では、主観によって達成しているかどうかの判断が分かれる原因になります。成果物を客観的に評価・管理できるようにするため、定量的な基準を設けましょう。
会議・コミュニケーションのルール
品質管理の仕組みが決まれば、次はプロジェクトメンバー同士のコミュニケーションルールを検討しましょう。
プロジェクトでどのようなコミュニケーション手段を用いて意思決定していくのか、中間報告(マイルストーン)はどのように実施するのかなどの要素が挙げられます。
会議にまつわることならメンバー同士の呼称や開催頻度など、あるいはコミュニケーションにまつわることであれば、プロジェクト管理ツールや議事録作成ツールは何を使うのかなどを決めるのが一般的です。また、普段やり取りするメールの件名も定めておくと、混乱なくスムーズにプロジェクトを推進できます。
起こり得るリスクと対策方法
どれほど綿密に計画を立てたとしても、プロジェクトが何のトラブルもなく計画通りに進むとは限りません。そこで、事前に考えうるリスクの洗い出しをしておくと安心です。具体的な項目としては、問題の重要度や発生しうる確率・頻度などが考えられます。
ただ、リスクの項目を挙げるだけでは、実際に問題が起きたときに最適な対処ができない可能性もあります。リスクの内容とともに、万一それが実際に起きた場合は、どのような対策を講じられるのかもあわせて検討しておくことが重要です。プロジェクト計画書に盛り込んでおくと、リスクに関するすべての情報を可視化でき、メンバーと共有しやすくなります。これにより、いざというときの迅速なリカバリーが可能です。
プロジェクト計画書を作成する手順
最後に、プロジェクト計画書の大まかな作成手順について解説します。工程ごとに大切なポイントも取り上げますので、ぜひ参考にしてください。スコープの定義
まずプロジェクトの目的とゴールを明確にし、プロジェクトの範囲を定義しましょう。プロジェクトを行う目的や必要となる条件、QCD(品質・費用・納期)のゴールを示します。目的は箇条書きにし、QCDはできるだけ数値化することがポイントです。 次に、明確化した目的に必要な作業を洗い出します。その際、規模の大きいタスクから洗い出し、細分化していくことがおすすめです。タスクをリスト化することで抜け漏れを防止できます。人的リソースの割り出し
次は、人的リソースの見積もりです。業務範囲(スコープ)が明らかになることで作業内容や作業量が判明し、必要な人数や人材が浮かび上がります。そのため、ここではタスクごとに必要な人数や割り当てるメンバー、外注が必要かどうかなどを検討します。組織図および役割表などを用いて、組織体制や役割が一目でわかるようにするのもポイントです。スケジュールの設定
全体の工期や着手する時期、マイルストーン、ローンチ日などのスケジュールを大まかに設定し記載します。メンバー間でイメージを掴みやすいよう、わかりやすく全体日程を記載し共有することが大切です。なお、詳細日程についてはWBS(作業分解展開図)スケジュールとして、別途で資料を作成しておくと便利です。
コストの計算
コストの計算は、必要なリソースやスケジュールに大きく関わっているため、リソースの割り出しやスケジュール設定後に行います。具体的には、設計や開発にかかるソフトウェア費用、機器・部品にかかるハードウェア費用、内部・外部人材も含めた人件費、インフラ費用や保守費用、備品費などを記載します。さらに詳細なコストは添付資料として作成しましょう。コストの計算により、資金繰りも実施しやすくなります。
リスクの確認
プロジェクトの工程で起こり得るリスクを洗い出し、その対策方法を記載します。具体的には、リスクの内容や発生する確率、影響度、優先度、対応戦略などです。もし、想定したリスクの影響があまりに大きい場合、プロジェクト計画の見直しを余儀なくされるかもしれません。トラブルが発生しても柔軟に対応できるよう対策案を出し、チームメンバーやメンバー以外の関係者全員とも共有します。
まとめ
プロジェクト計画書は、プロジェクト実現の確実性を高めるほか、関係者全員で共通認識を持つために必要な資料です。計画書の作成は、目的やゴールを明確にして、目標達成に必要なタスクやリソースを洗い出すことから始めます。
さらに、考えられるリスクを確認し共有しておくこともポイントです。プロジェクト中のトラブルに対応し、プロジェクト計画の早期実現につなげられます。
「Asana」は、プロジェクト計画・管理・追跡・意見交換に活用できるワークマネジメントツールです。タスクの状況が一目でわかるボード機能や、タスク同士の連携を視覚化したタイムライン機能など、プロジェクト計画に便利な機能がそろっています。また、プロジェクトの目標やマイルストーンがトラッキングできるため、認識共有も簡単に行えます。プロジェクトを円滑に進めるためにも、ぜひ導入をご検討ください。
- カテゴリ:
- プロジェクト管理