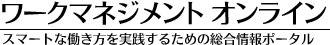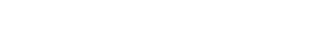製造業のDXとは? 日本のものづくりをDX化するための課題と取り組み方
日本の製造業の多くは、人手不足や技術継承の困難化、設備の老朽化、災害を含む不測の事態に備えるためのサプライチェーンの強化など、多岐にわたる課題を抱えています。こうした課題の解決策として、DXの推進が挙げられます。この記事では、製造業でDXが求められる背景や、DXを推進するメリット、DXを進める手順などを詳しく解説します。

製造業のDXとは?
DX(Digital Transformation)は、デジタル技術を用いた変革を意味する言葉です。また、DX推進は、企業などにおいてDXを推し進める取り組みを指します。業務を見直し、必要な箇所にデジタル技術を導入することで、品質や生産性の向上などさまざまなメリットを得られます。例えば、製造現場にAIが搭載されたロボットを導入することによって業務の自動化・省人化が実現すれば、現場の従業員の負担を減らし、人材不足の解消につながる効果が見込めます。
製造業におけるDXでは、AIやセンサー機器、管理システムといったデジタル機器の導入によって、効率化や品質向上、生産性向上を目指します。アナログな製造現場をデジタル技術で効率化することで、顧客提供価値やQCDの向上、企業内のノウハウのデータ化・共有化を実現することが可能です。また、データの共有や活用はデータドリブンな判断に役立ちます。これにより、顧客や社会のニーズを従来より迅速かつ正確に捉えやすくなり、ビジネスモデルの変革や事業機会を拡大するチャンスを得やすくなります。
製造業のDXとスマートファクトリーの違い
製造業におけるDXは、全体におけるデジタル化を指し、製造プロセスの改善や生産性向上を目指す取り組み自体を指しています。一方でスマートファクトリーとは、AIやIoTなどのデジタル技術を工場の機器や管理システムなどと接続し、データ収集による業務工程の管理やデータ活用を可能とする工場のことです。
どちらも生産性や品質向上を目指してデジタル技術を活用する点が共通しています。製造DXとスマートファクトリーの違いは、前者がビジネスプロセスの変革を伴う取り組みを指すのに対し、後者は現場のデジタル化とデータ活用を推進する工場を指す点にあります。つまり、スマートファクトリーとは、製造業DXの一環であるといえます。
製造業でDXが求められる背景
製造業では、少子高齢化に伴う人手不足や自然災害への対応といった社会課題へ適応するためにDXが推進されています。人手不足
DXが求められる最大の理由が人手不足です。少子高齢化や労働人口の減少に伴い、製造業界は慢性的な人手不足に悩まされています。経済産業省と厚生労働省、文部科学省の3省で共同作成された「2023年版 ものづくり白書」によると、2022年における製造業の就業者数は1,044万人と、2002年の1,202万人から約158万人も減少しています。全産業に占める製造業の割合も同じく19.0%(2002年)から15.5%(2022年)と下降傾向です。以上のデータから判断して、製造業における人手不足の改善は短期的には期待できないと考えられます。
人手不足は、長時間労働の常態化やそれに伴う従業員の負担増などの悪影響をもたらす要因です。このような問題がある就労環境を放置すると、さらに働き手が遠ざかる事態につながり、人手不足の悪循環に陥ってしまう恐れがあります。このような現状に対しては、賃上げが有効な手段です。しかし、そのような措置により人件費が増加し、低コストで生産できる海外との競争力が低下するというジレンマが生じます。
その他にも、人手不足は技術継承の困難化、人材獲得競争の激化、国内の人口減によるマーケット縮小など、さまざまな影響をもたらすため、DXが課題解決の手段として注目されています。
参照元:2023年版ものづくり白書(全体版) ※P.42をご参照ください。
進まない設備投資・老朽化
日本では設備投資に消極的な企業が多く、設備の老朽化が進んでいることも、製造業でDXが求められる要因のひとつです。経済産業省が2021年に公開した資料「製造業を巡る動向と今後の課題」によると、製造業における設備投資額が減少していると報告されています。設備導入から15年以上経過した生産設備が多くの割合を占めるなど、老朽化も課題です。
参照元:製造業を巡る動向と今後の課題 ※P.5をご参照ください。
先に紹介した「2022年版ものづくり白書」において、2017年度から2020年度の平均値で営業利益率が高い企業は、有形・無形の設備投資や研究開発投資を積極的に行っていることが報告されています。その一方で、営業利益率が低い企業は設備投資が少なく、借入金増加率も高いことが明らかになっています。
一方、2020年前半から落ち込んでいた製造業の設備投資額は増加傾向を示しており、現在も継続中です。特に脱炭素関連、システム・DX投資の伸びが目立っています。設備の更新が遅れている企業は、こうした設備投資の流れに乗り、生産力を高めていくことが重要です。
参照元:2023年版ものづくり白書(概要) ※P.19をご参照ください。
感染症や自然災害の激甚化
感染症や自然災害などの予測不可能な事象から受ける影響が大きい点も、製造業でDXが重要視される理由です。近年では新型コロナウイルス感染症の影響によって、海外から部品が届かないなど安定的な生産が困難となる状況に陥りました。
また、自然災害が発生した際に、被害の影響でサプライチェーンの流れが一部でも止まってしまうと、生産計画に大きな混乱が生じる可能性があります。サプライチェーンが国外に広がっていることや、自然災害が増加していることを考慮すると、これは決して無視できないリスクです。
さらに、世界情勢の影響を受けて原油価格が高騰するといったエネルギー問題も考慮する必要が出てきています。こうした難しい状況が続く中、十分な対策ができている企業は多くありません。先行き不透明な時代を生き抜くためにも、日本の製造業は抜本的な生き残り戦略を立てる必要が求められています。
製造業のDXを進める5つのメリット
製造業がDXを推進することでさまざまなメリットが得られます。その中でも、特に注目すべき5点を紹介します。1.情報が可視化される
業務のデジタル化や製造現場へのIoT機器の導入によって、製造や設備の状況をリアルタイムに把握可能です。これによって、工場内のあらゆる情報を可視化できます。例えば、カメラやセンサーで機械の稼働状況を常時モニタリングすることで、人による目視よりも機械の劣化部分を高精度に特定しやすくなります。
また、在庫状況や作業の進捗状況をシステム上で管理すれば、現在の状況を即時に把握できます。在庫管理や人員配置を最適化できるようになり、生産性の向上が可能です。万一トラブルが起こった際も、収集したデータから円滑に問題を特定し、速やかな改善につなげられます。
属人化している作業がある場合は、データを他の従業員と共有することで作業品質水準の均一化が図れます。生産・販売データを組織全体で共有することは、新しいアイデアやナレッジの創造などに効果的です。
2.生産性が向上する
デジタル技術を活用した業務プロセスの改善によって、生産の質が向上します。例えば、人の手による作業をロボットに代替することで、作業の品質を安定させ、かつ時間を短縮できます。機械化によって稼働率が上がるうえ、24時間の稼働も可能です。
非効率的でアナログな作業をAIに任せて自動化することは、従業員の負担軽減や生産性の向上、ひいては人手不足の解消に寄与します。危険な作業がある場合も、機械化によって作業現場の安全性を向上し、労災リスクを低下させられます。
生産工程や生産量の最適化を実現するには、生産データが役立ちます。これにより、人的リソースを削減しながら生産効率を向上させることが期待できます。また、機械やAIが単純作業を代わりに行うことで、従業員をコア業務に専念させることも可能です。
3.技術継承が円滑になる
日本のモノづくりはこれまで熟練の職人が持つ勘と経験に依存していた部分が大きく、ノウハウが属人化している問題がありました。同時に、少子高齢化による人手不足の問題も重なり、次世代への技術継承が進んでいない状況です。
これまで熟練技術者に属人化していたノウハウや技術のデータ化を進めることで、こうした課題を解決し、後継の育成につなげられます。例えば、VRを利用した訓練やオンライン学習プラットフォームの活用、動画マニュアル作成、熟練技術者が持つノウハウのデータ化と共有といった方法で、熟練の技術を学ぶ際に役立てられます。それによって属人化を脱却し、技術継承を円滑に進めることが可能です。
4.ダイナミックケイパビリティが高まる
製造業のDXを進めることでデータドリブンな判断が可能になり、ダイナミックケイパビリティ(企業変革力)が高まるというメリットがあります。
データドリブンとは、企業活動のプロセスで集まったビッグデータを分析し、その結果に基づいて意思決定や施策立案を行う手法のことです。DXにおいてデータドリブンを実現する例としては、需要予測の精度向上が挙げられます。販売データや在庫数、顧客データなどを分析することで、高精度な将来の需要予測や予測に基づく仕入れの最適化が可能です。
このようなデータドリブンを採り入れた業務効率化やDXを担える人材育成が進むほど、企業内ではデータドリブンな判断が当たり前になります。そうなると、これまでよりも市場の変化をデータから正確かつ敏感に察知できるようになることが期待できます。
経済産業省の「2023年版ものづくり白書」では、ダイナミックケイパビリティについて、企業が「脅威や危機を早期に感知」し、「既存の資産や技術を再構成」した上で、「競争力を持続的なものにするために組織全体を変容する」変革力と定義しています。市場や社会、顧客のニーズといった外部環境の激しい変化に対して柔軟に対応するため、利用できる資源を再構成し、競争力も確保しながら企業自ら変革していく力のことです。
参照元:2023年版ものづくり白書(全体版) ※P.152をご参照ください。
ダイナミックケイパビリティが重視される主な理由として、感染症や自然災害がもたらすリスクが挙げられます。先述のように、これらは外部環境の変化の中でも予測不能かつ急激な変化を伴う事象です。今後も同様の困難な状況が発生する可能性が考えられるため、企業はDXの推進によってデータドリブンを採用し、ダイナミックケイパビリティを高めておくことが重要になります。
5.顧客満足度が高まる
DXは顧客満足度の向上にも効果的です。例えばデータによる情報の可視化が進むことによって、製造工程の効率化、在庫状況の把握、人員配置の最適化などが容易になります。その結果、品質管理の強化、コスト削減、生産効率の向上などに寄与します。こうしてエンジニアリングチェーンやサプライチェーン全体が最適化されることで、生産プロセスの効率が向上し、顧客満足度の向上が実現できます。
また、顧客の細かい声を拾いやすくなる点もメリットです。システム上で顧客情報管理を行うことで、顧客のニーズや要望、好み、トレンドなどのデータ分析がしやすくなります。その結果を基にマーケティングを展開したり、アフターフォローを充実させたりすることが可能です。
DX導入の手順
製造業においてDXを実際に推進する方法は、業種や企業規模などによって異なるものの、おおむね以下のような手順で行います。
- 社内の課題や業務フローを見直す
- 解決すべき課題や現場の意見に合ったシステムやツールを検討
まずは、導入前に現状の課題や業務フローを洗い出す作業をする必要があります。この段階では、DX推進における目標の明確化や、改善を図るべき作業工程を把握しましょう。特に業務フローにおいては、実際に働く現場の意見をヒアリングすることで、より正確に把握できます。
次に、上記の作業で得た知見を基に、自社に合ったシステム・ツールを選定します。導入にあたっては、コスト面や使いやすさ、サポートの充実度などに注意しましょう。また、スモールスタートから始めることもポイントです。業務全体を一気に変更すると現場が混乱するだけでなく、失敗した際の負担も大きくなります。まずは特定の部署や一部業務から導入して、効果検証を繰り返しながら、徐々に適用範囲を広げていく方法が効果的です。
製造業のDX化を進めるうえでの課題とは?
DX推進は多くのメリットをもたらしますが、一方で生じ得る課題も押さえておかなければなりません。優秀な人材の確保
製造業に限らず、企業がDXを推進する際によく課題となるのが優秀な人材の確保です。経済産業省が公表している「令和3年度製造基盤技術実態等調査」では、企業がデータ連携を進める上で生じる課題についてのデータが示されています。製造業2万5,000社を対象に実施したアンケートにおいて、業務プロセス間でのデータ連携を進める上での課題について質問したところ、「データ連携を実施する人材の欠如」を挙げた割合が56.8%と最も多い割合を占めました。また、デジタル人材の確保の必要性を聞いた設問では、約7割の企業が「必要である」と回答しています。
参照元:令和3年度製造基盤技術実態等調査 我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査報告書 ※P.137、P.155をご参照ください。
このように、多くの企業がDX関連の人材不足を自覚している状況です。しかしながら、DX推進を担える専門人材には高度なスキルが求められるため、全体的に人材不足の傾向にあります。人材確保にあたっては、社内でDXに精通した人材を育成する方法もありますが、それには本格的な研修プログラムを組む必要があります。自社で実施する場合、コストと時間がかかってしまうだけでなく、ノウハウがなければ十分な効果は得られません。
データを利活用する体制づくり
製造業において、データ活用は全体的に進んでいない状況です。先述の「令和3年度製造基盤技術実態等調査」によると、生産プロセスに関するデータ収集を行っていない企業は半数近くに上ることが明らかになっています。また、業務プロセス間でのデータ連携を進める上での課題についての設問では、「データ連携にかかる知識不足」や「各部門の理解の欠如」が上位に挙がっており、知識・理解不足がデータ活用の妨げになっていることが明らかとなりました。
参照元:令和3年度製造基盤技術実態等調査 我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査報告書 ※P.166、P.137をご参照ください。
データを活用できる体制を構築するには、デジタル機器を導入する前に、まず何より知識や理解を深める必要があります。まずは社内の理解を得て、部署間で連携を取りながらDXを進めなければなりません。
自社に合ったツールの選定
自社に合ったツールの選定も重要な課題ですが、それには事前の準備が欠かせません。まずはDXの目的と解決すべき課題を明確にすることが必要です。目的が曖昧なままでは効果的なツールが選定できず、DX推進に失敗する可能性が高くなります。
その上で、実際に導入するツールの選定を行います。検討すべきポイントとしては、現場の従業員が使いやすいものか、課題解決につながる機能が備わっているか、導入後のカスタマイズは容易か、アフターサービスやサポート体制が充実しているかなど、多岐にわたります。
そもそもDXに詳しい人材がいない場合、自社に合ったツールを選ぶこと自体が困難です。合わないツールを導入してしまった場合、かえって作業が複雑になったり、使いこなせなかったりする可能性が考えられます。そのため、詳しい人材がいない場合は外部の専門家や支援サービスを活用しましょう。
DXに取り組む際の注意点とは?
製造業においてDXに取り組む際には、いくつかの注意点があります。まず、DXの推進にあたっては、自社がDXを必要とする理由となる課題に焦点を当て、解決に向けてDXと同時に取り組む必要があります。また、導入コストやセキュリティ対策も意識しなければなりません。業務の見直しや社内環境の整備と共に取り組む
DXはそれ自体を目的として推進するのではなく、必ず業務の見直しや社内環境の変革を目指します。そのため、業務プロセスの見直しや生産性の向上を継続的に行うことが重要になります。
また、人手不足が懸念される中で人材を確保するためには、既存の価値観にとらわれず、女性や高齢者など多様な人材を活用することも重要です。幅広い人材が活躍するためには、柔軟な働き方ができる社内体制を構築する必要があり、DXもそれを実現するためのものでなくてはなりません。 漠然とデジタル化を進めても、自社の課題を解決するというゴールを設定していなければ、十分な成果は得られません。DXを実行する際は上記のような課題を認識した上で、それらを解決するための手段として推進することが求められます。
導入コストを把握する
システムやツールを導入するためには、まとまった時間とコストが必要です。もしも資金を準備するのが難しい場合は、国が実施している「IT導入補助金」や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)」などを活用して資金を調達することも検討しましょう。
また、DXの推進にあたってはデジタル関連に強い人材も必要です。そうした人材の確保が難しい場合は、外部の専門家に相談したり、業務のアウトソーシングを活用したりして対応することが必要です。
セキュリティ対策をとる
DXを推進する際にはさまざまな情報をデジタルデータ化する必要があるため、セキュリティ対策に取り組むことも重要です。セキュリティが脆弱な場合、サイバー攻撃を受けるなどして大きな損害を被る可能性があります。そのため、自社の機密情報が外部に漏えいしないよう、強固なセキュリティ体制を構築する必要があります。併せて、研修などを通して従業員の情報リテラシーも高めるようにしましょう。まとめ
日本の製造業は、少子高齢化や人口減、就業者数の減少を背景とした慢性的な人手不足や設備の老朽化といった課題を抱えています。また、自然災害や感染症、世界的な情勢不安といった予測不可能な事象の影響も受けやすい点も課題です。こうした状況に備えるためには、DXの推進が不可欠です。製造業のDXを推進することで、従業員の業務負担の軽減、生産性向上、技術継承の円滑化、ダイナミックケイパビリティの向上を実現し、事業の持続可能性を高められます。
スイスの織機製造業者であるRieter社では、ワークマネジメントツールAsanaを用いて日々の業務を行っています。ワークマネジメントツールは、同社の働き方を深くサポートします。Asanaのソリューションによって生産性が向上したと回答した従業員は全体の3分の1、さらにそのうちの3分の1の従業員は、「著しく」向上したと答えています。
ぜひ以下の資料で詳細をご確認ください。
- カテゴリ:
- DX(デジタルトランスフォーメーション)